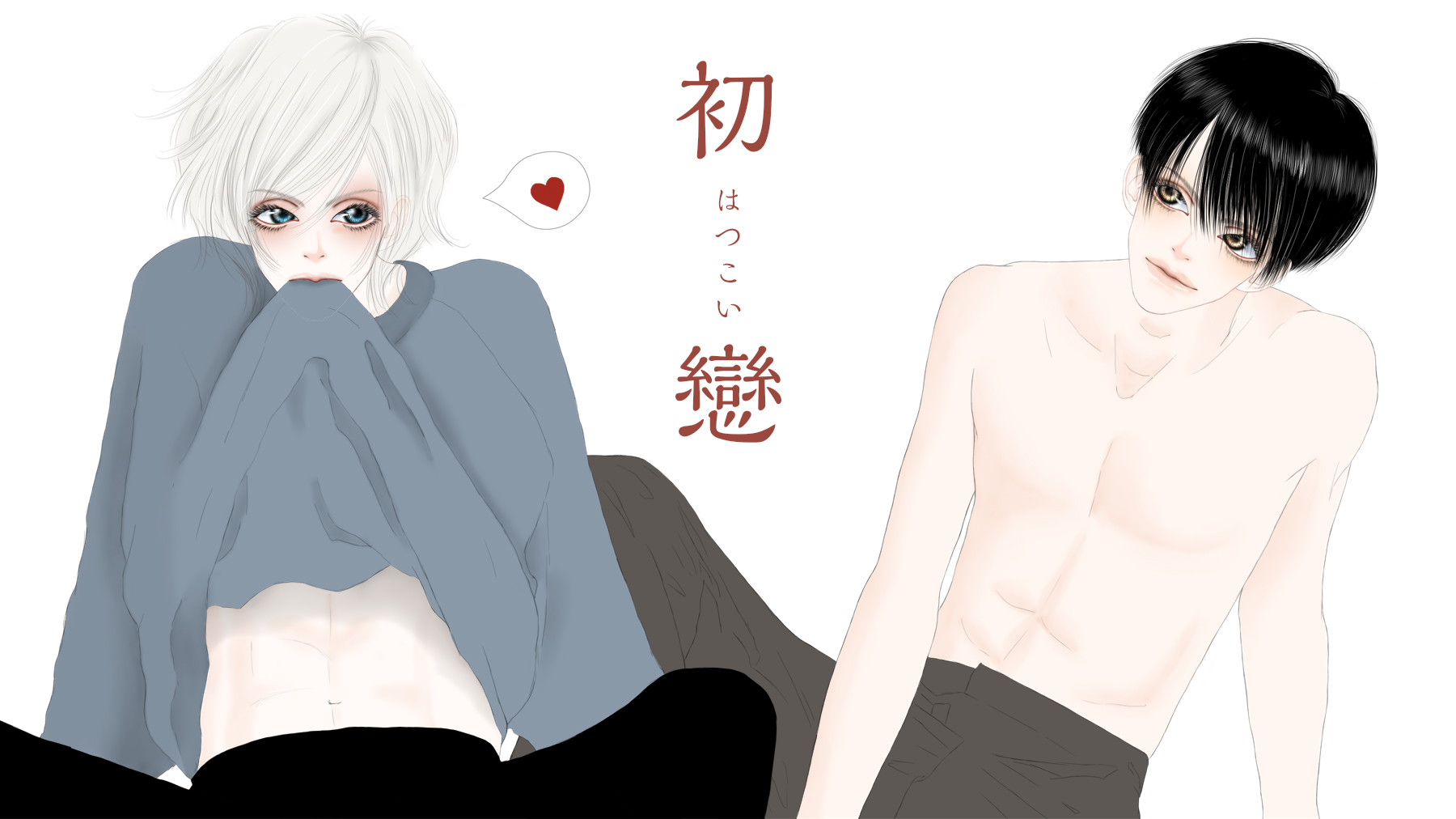第五十四話 賽は投げられた
「…よし、登録…と」
「こっちも登録したで、真正のドMです、て」
「うち、緊縛プレイでしか興奮できない体質なんで、てコメント書いたった」
「あの、さっきから三人で何してるの?」
久御山とシロくんとクロくんは、病室に来るなりずっとスマホとパソコンを触っていた。
「ゲイ御用達の出逢い系サイトに登録してんの」
「……久御山?」
「ちがっ、違うから! オレのじゃないから!」
「ふうん…僕に飽きたんならそう言ってくれれば」
「違うって! ちなみにそう言ったらどうなんの?」
「A.秒で他のひとと合体する B.満面の笑顔でじゃあ元気で! と言う どっちがいい?」
「C.絶対飽きないんで捨てないでください」
「D.湊とうちらがしあわせに暮らす、どや?」
「シロクロまとめて登録すんぞオラ」
どうしてそんなサイトに登録してるのか、理由を聞いて背筋が寒くなった。
「ちびっと警視庁本部のサーバー覗いたらな、防犯カメラシステムの映像あってな、解析してみたらなんやけったいなヤツ四人ほど写ってたさかい、なんやろなあ思て調べてん。ほならこの辺の大学生みたいでな、イベサーゆうの? けったくそ悪いサークル入ってて」
「なんやえげつないことようけしてるみたいやし、そゆのんお好きなんやなあ思て。そないお好きならうちらが手伝ったろ思てな、出逢いはようさんあったほうええやん? そやから連絡先ちびっと調べて出逢い系アプリに登録したったん」
「もう二、三人食い付いて来たはるから、個人的に遣り取りして逢う算段付けててん」
「バイトのあがり時間わかったから、いにしなに逢えたらええなあ思て」
「時間と場所指定して」
「あらくたいプレイがええから、嫌がるフリするけど構わんとヤってな、て」
「まあ、しばらくは遊び相手に困らんのとちゃうかな」
「二日に一回くらいのペースで、なんしかえげつないプレイしてもらわれはるやろ」
シロくんとクロくんは楽しそうにそう言ったけど、目が笑ってなかった。これは、僕の仇討ちってことなんだろうな……偶然警視庁のサーバー覗くなんて、タイミング良過ぎるだろ…
※ けったいな:おかしな / けったくそ悪い:忌々しい / えげつない:残酷、あくどい / いにしな:帰る途中 / あらくたい: 乱暴な / なんしか:とりあえず
──
「藤城さん、面会したいという方がいらっしゃっているのですが」
昼過ぎ、日中の新宿のクリニックを担当してる榊先生が少し訝し気に言った。
「面会? 僕に?」
「こちらに入院されているのをご存知なのはお身内の方だけのはずですが、お母さまに伺ったとかで…」
「母に? 誰だろう…」
宗さんから話を聴いたはずの母は、まだ面会に来ていなかった。ここに運び込まれて四日目……母は僕の顔が見れないんだと思った。母が悪いわけじゃないのに、きっと母は自分を責めて苦しんでいる気がした。大丈夫だよ、なんて言葉を掛けたとしても、母の心は晴れない。
病室の扉がノックされたあと、すっと音もなく開いた入口に視線を向けると、スーツを着た男のひとが会釈をしながら部屋に入って来た。
「久しぶりだね…三年振りかな」
「……せ…」
「仕事の都合でこっちに来たんだけど…入院してるって聞いて驚いたよ」
── 先生…
***
「は? いなくなった?」
桐嶋から電話だなんて嫌な予感しかしない、と思いながら電話に出たらやっぱり嫌な話だった。
「トイレとか風呂とか散歩とか」
「トイレも風呂も部屋にあるし、散歩できるほど足は回復してねェよ」
「いついなくなったんだよ」
「わからん…榊の話では昼過ぎに面会に来たヤツがいるとかで、それ以降らしいが」
「……面会? 誰だよ」
「俺が知るわけねェだろ…時間外だぞ」
「シロクロに言って探してもらうとか」
「防犯カメラに引っ掛からねェんだとよ」
防犯カメラに引っ掛からない? 湊にそんな特殊な訓練が身に着いてるとは思えないんだが。とりあえずクリニックに行かないことには何がなんだかサッパリわからない。
急いで新宿のクリニックに行くと、受付に榊さんが座っていた。新宿のクリニックは基本夕方からの診療らしいけど、どうしても昼にしか来られないひとのために、予約診療はしてるとか。それにしても榊さんて医師みたいだけど、受付もやっちゃうのか……その強面で…
「榊さん、面会に来たひとってどんなひと?」
「スーツ姿のきちんとした方でしたよ…あ、面会者の記録ありますけど」
「なんて名前?」
「七種 基成さん……ご存じです?」
「知らないな…誰だろう」
「眼鏡を掛けた優しそうな…二十代後半くらいの」
「……そのひとと面会したあと、いなくなったんだよね?」
「面会のあと、というか途中というか」
「途中?」
「ええ、十五分くらいで七種さんが降りて来られて、藤城さんが戻って来ない、と仰って」
オレの勘に間違いがなければ……いや、できれば間違いであって欲しい。二十代後半の優しそうなスーツの男、なんて思い付くのはひとりしかいない。この二年間、そいつ以外で該当する知り合いの話なんて聞いたことがないんだ。足の裏の怪我も治ってないのに、姿を隠さなくちゃいけない相手…
一階は診察室や処置室があってひとの出入りがある。二階は事務所と桐嶋の院長室。三階に今回みたいな場合に使う病室が二部屋。四階と五階はマンションになってて、榊さんや他の医師が住んでるらしい。身を隠せる場所は限られてるけど、簡単に見つかる場所では隠れる意味がない。
非常階段やトイレ、リネン室、倉庫……多分そういう場所じゃない。
五階まであがると、屋上に出るための扉があった。非常ベルとか鳴ったりしないだろうな、と思いながらそっと開けると、目の前に屋上庭園が広がっていた。あれか、 “東京における自然の保護と回復に関する条例” のせいなのか、それとも桐嶋の趣味なのか。
小さな公園のような屋上庭園をぐるりと見渡すと、木々の隙間から湊の背中が見えた。無防備に手すりに腰掛け、黙って空を仰ぐ湊は昔のままの……見つかるまいと集団の中で息をひそめる、被食獣のような儚さでそこにいた。
声を掛けることさえ躊躇ってしまうほど、酷く傷付いた顔で空を見上げたまま、湊は震える声で小さくつぶやいた。
「背中、押してくれる?」
両手は膝の上で握られ、風に煽られただけでその身体は、支えるものも遮るものもなく思った通りの結果を得られるだろう。オレはよっこいしょ、と手すりを乗り越え湊の目の前に立った。ビルの縁はさほど厚みもなく、踵が少しはみ出した不安定な状態だったが不思議と怖くはなかった。
「おいで、湊」
腕を広げて笑うと、湊は ── 大慌てでオレの腕を掴んで引っ張った。
「バカ、久御山! 落ちたらどうするんだよ! ちょ、早く戻って来い!」
「バカっておまえ……背中押すよりいいと思ったのに…」
「全っ然よくないだろ! とにかくこっち来いって!」
オレの腕をしっかり掴んだまま湊は手すりから降りて、それからオレの制服の襟を掴んで「早くしろって!」と声を荒げた。
「心臓、止まるかと思った」
手すりに腰掛ける湊を見た瞬間、いまにも落ちるんじゃないかって心臓がギュっと縮んだ。そう言って湊を抱き締めると、それ以上の力で湊がオレの首にしがみ着いた。
「ねえ湊、オレおまえがいないと生きて行けない」
「……ごめん…」
「だから、背中は押せないけど」
「…うん」
「そう思ったおまえを、この世界から守りたい」
「……くみや…」
「七種って……カテキョ?」
「…ん…そう…」
「なんかされた?」
「されてない…」
屋上庭園のウッドデッキにあるベンチに腰をおろし、向かい合わせで膝の上に湊を乗せた。痛くない? と訊くと大丈夫だよ、と湊はおとなしく膝の上に納まった。
「何しに来たの? 地元で就職したって言ってなかった?」
「……中学校の教員なんだって」
「は?」
「非常勤として半年ほどこっちにいるって」
「なんの冗談だよ…中学校の教員なんて」
「…結婚してこどももいるって」
「それがいまさら湊になんの用だよ」
「久しぶりに……顔見たかったって…」
「もう見たんだから二度と来んな」
「……何もされなかったけど…」
「けど?」
「……写真…まだ削除されてなくて…」
「写真? スマホの?」
「うん……連絡…拒否したらお母さんに見せるって…言われて…」
「……東京湾に沈めて来る」
多分クラウドにバックアップ取ってあるだろうから、スマホ壊したところで何の解決にもならないだろうな……果たして湊の写真だけなのか、他の “男の子” の写真もあるのか。シロクロに言ってクラックしてもらうとか…ローカルに保存してあったらどうする? 機種変前の端末とか。
「…湊、今回の件て宗弥さんは知ってるんだよね?」
「うん…ここから久御山に連絡してもらったから」
「カテキョの件、知ってるのはオレだけ?」
「うん…お母さんはいい先生だと思ってるから…」
「遥さんに知られるのは嫌か?」
「……写真とか動画で知られるのは…お母さんもつらいと思うから」
「ん、それはわかってる」
「……久御山」
── 僕は…最初は無理矢理だったけど、そのあと先生と関係を持ち続けたのは僕の意思だよ。かばうとかじゃなくて、事実として僕は受け入れてたんだ。理由はともかく、僕が望んだことなんだよ。
「だから?」
「一方的に先生だけが悪いわけじゃ…」
「過去のことを断罪しようなんて思ってないよ。オレの知らないことも、オレにはわからないこともあっただろうし。でもね、これから先に関しては何ひとつ赦さないし認めない。実害が及ぶなら出るとこ出るよ」
「ごめん、久御山……ごめん…」
「おまえが謝ることなんてなんもないよ…おまえは悪くない」
膝の上の湊を抱き締めながら、どうすることが最善なのか、脳細胞を総動員して考えた。
──
「転院したい?」
「もしくは退院させて欲しい」
屋上庭園から戻ったオレは湊に部屋の鍵を掛けさせて、時間外だという桐嶋と外で逢った。普通の高校生なら入ろうとも思わない昭和の香りのする薄暗い喫茶店で、桐嶋は腕を組んで難しい顔をした。
「性的暴行に関しては、こっちでフォローアップできるんだが」
「ああ、感染症とかHIVの話ね、それは通院すればいいと思う」
「言いたくねェなら言わなくて構わねェんだがな」
「…何か気になることでもあんの?」
「藤城……レイプされるの初めてじゃねェんだろ」
「……それ、オレが気になってることと関係ある話?」
「気になってること?」
「レイプされたひとって、次の日普通に笑って話せるもん?」
「その辺の話は簡単じゃねェんだよ…」
── 被害を即認識して理解して訴えることのできるヤツもいるだろうが、正常性バイアスが掛かってたり、同調性バイアスが掛かってたりして被害を「正常な範囲内のことだ」と思っちまうヤツもいる。自分に悪いところがあったんじゃねェか、つって悩むヤツだって多いんだ。
普通にしてりゃ前と変わらねェ生活が送れる、とか自分さえ黙ってりゃいい、とかレイプじゃなくて愛のある行為だった、とか自分を救うために一所懸命思い込もうとすんだよ、奈落の底でな。だから見た感じ普通に振る舞う。
通常、防衛機制ってのが働くんだが…つらい現実を認めたくない「否認」、被害を小さなもんだと思い込む「最小」、間違いだとわかっていても自分を正当化する「合理化」っつー防衛機制を繰り返して、本人はどんどん疲れちまう。そのうち生体エネルギーが枯渇して、防衛機制が破綻する。
そうやってASD(急性ストレス障害)からPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症して、不眠、摂食障害、嘔吐、呼吸困難、過呼吸、目眩なんかを起こすようになって、人間不信こじらせて孤立したりすんだよ。自棄的になってるから尚更な…自分にも他人にも期待なんかしなくなる。
「藤城は多分……自分の気持ちを言語化できねェくれェ小せェ頃に被害に遭ってる」
「……なんでそう思うの?」
「そのあと思春期を自覚する前に何かあったんだろ」
「アンタ、本当に医者だったんだな…」
「血も涙もねェヤクザモンだとでも思ってたのか?」
桐嶋は…桐嶋先生は笑いながら冷めたコーヒーに口を付けた。
「気持ちを言語化して外に吐き出せねェこどもはな、大人に言われたことで気持ちを上書きすんだよ」
「どういうこと?」
「あー、たとえば加害者から “きみは悪い子だね” とか “恥ずかしいことしちゃったね” とか “誰にも言っちゃ駄目だよ” とか “知られたら怒られるよ” とか言われるとな」
「自分は、知られたら怒られる恥ずかしいことをした悪い子だから黙ってなくちゃ、って思い込む?」
「そーゆーこと…それを自分の中でずっと育てちまう」
「湊は…小学生の時変質者に遭って、中学の時家庭教師に手籠めにされてる」
「…なるほどな」
「でも本人は…最初は無理矢理だったけど、それ以降は自分の意思でヤってたって言うんだ」
「そりゃそうだろうよ」
── 第二次性徴が来て性的関心が起こるもんだが、その前に性的快感覚えさせられりゃ、心は未熟なままカラダで解決するようになんだろ。悪い子のはずの自分に快楽を与えてくれる相手が悪人のはずがねェよな? 性的関心が起こる前に快感で手懐けられて、その家庭教師だけが自分を必要としてくれてる、と思っちまう。
「藤城、多分先祖返り起こしてんぞ」
「先祖返り?」
「家庭教師にヤられてた頃に戻っちまってんだよ、心が」
「……あんな酷い目に遭ったのに?」
「だからだよ…レイプされて、以前同じように扱われてたのを思い出したんだろ」
「だったら、フラッシュバックとかでパニクったりするんじゃないの?」
「その家庭教師は、悪い子に快楽を与えてくれた善人だぞ?」
「……冗談じゃねえ」
「藤城が取り乱さねェ理由がわかったよ……あいつにしてみりゃ、いま過去の日常を繰り返してるだけなんだ」
「それを当たり前だと思ってるわけじゃない…さっきだって屋上の手すりに手放しで腰掛けてたんだ…」
「言葉で上書きされた気持ちの、やり場がないんだよ」
「嫌なことされて、我慢して、我慢してるのが身に着いて、死にたくなってんのに笑ってるなんて苦しいだろ…」
「……被験体だったおめェも、同じだったんじゃねェのか」
「おこがましいけど、オレは湊を救いたい」
桐嶋先生は笑うように溜息を吐いて、カップに残ってたコーヒーを飲み干した。それからもう一杯コーヒーを頼み、オレの顔をしばらく眺めたあとで、今度は本格的に溜息を吐いて「もうひとつ気になることが」と話し始めた。
「……いま…なんて…?」
オレの耳は桐嶋先生の言葉を一言一句聞き逃すことはなかったが、信じたくない気持ちが音を立てて膨れ上がったせいで聞き間違えたのかもしれない、と憐れにもそう思い、訊き返した。