第七話 暗闇の猫は皆灰色
「藤城くん」
……中学にあがり、学校で女子に話し掛けられるのは初めてだった。あれ、僕何か忘れてたかな……宿題、日直、掃除当番、委員会……どれも思い当たる節がない。
「な、なに……?」
「あの……これっ……」
人気のない階段の踊り場で、目の前に封筒と紙袋を差し出された。
「えっと、これは……」
「かっ、家庭科の授業で作ったの、あの、ラッピング用の袋もあってね、言ったら先生がくれるの」
「あ、うん……そうなんだ」
「あ、中身ね、クッキーなの。よかったら……もらって欲しいなって思って」
「……え、僕に?」
「うん、そう、藤城くんに」
「え…っと…どうして?」
「手紙、書いたの。読んでくれたら…あの、読んでください」
封筒と紙袋を受け取り、ありがとう、と言ったらその子は「じゃあ」と言って走り去った。突然の出来事に、僕はしばらくその場で立ち尽くした。
家に帰ってもらった手紙を読むと、書いてあることが別世界の話のように思えた。
彼女は隣のクラスで、同じ図書委員をしていること。それから、僕が返却された本を丁寧に確認し、どんな小さな傷でもマメに修復すること。毎日図書室の床を掃き、机を拭いていること。
一度だけ……放課後の図書室で僕が居眠りをしていたこと。
その姿がとても幻想的で、まるで本から抜け出して来たように見えたこと。
……僕は「やらなくちゃいけない」という義務感からそれをしていたに過ぎず、まさかこんなに好意的に見てくれてるひとがいるなんて思いもしなかった。当然、そんなことをきっかけに僕に告白するようなひとがいることも。
「……湊、これ何?」
「あ、クッキーだって言ってた」
先生は机の上にある紙袋をそっと横に避けて、その下にある封筒を手に取った。
「へえ……いまでもラブレター書く子なんているんだなあ」
「ちょっ…それは」
「…………すごいな、ベタ惚れじゃん彼女」
「先生、お願いだから返してよ…」
「うん、でも気持ちはわかるよ……湊、美少年って感じだし」
「そんなんじゃないって…手紙返して」
「本から抜け出した王子さまに恋する女の子、か」
先生はそう言うと、僕のシャツをたくし上げ乱暴に乳首をつねって耳元で囁いた。
「……おまえの正体、知らないもんな」
手で口を塞がれ萎えたモノを揉みしだかれながら、僕は机にしがみ着いた。
「王子さまがヨダレ垂らしながら欲しがってんの、見たらどう思うんだろうね」
やめて……なんでそんなこと……
「女の子にしゃぶられてもエロい声出してイっちゃうのかなあ」
やめて……
「この子に見せてあげようか……王子さまが涙浮かべながら射精するとこ」
やめて……
「いつもみたいにエロい顔して誘ってみれば? 気持ちイイこと大好きじゃん王子さま」
やめて……
「イイ声で鳴けよ……お母さんにバレないようにな」
次の瞬間、目の前が真っ赤になった ──
「…ぐ…っ……!」
痛い痛い痛い痛い痛い……!! 先生、痛い……!
「力抜けよ……いままで舌で慣らして来たんだから大丈夫だよ」
痛い……先生、大丈夫じゃない……先生……先生……!
「すごい締まるね、湊……あ……湊のカラダ気持ちイイ…」
やめて……先生、お願いだからやめて……痛いよ…先生……
「おまえ、本当にエロいんだな……ガチガチに勃ってんじゃねえか」
……壊れる……
「次は優しくしてあげるね」
先生はそう言って僕の頭をなでた。
「……痛い…」
どうしてこんなこと……先生はどうして僕にこんなことをするんだろう……僕がいやらしい子だから? 恥ずかしいことされるの大好きだから? 僕がエロいから? 欲しがりのビッチだから? アナル吮められながらイっちゃうから? エロい目で誘うから? 気持ちイイことされるの大好きだから?
無理やり突っ込まれて……それなのにガチガチに勃たせてるエロいビッチだから……?
僕はいつから……メス犬になったんだっけ……
指先に付いた血が僕を嘲笑う。おまえのカラダは男を受け入れたんだ、と現実を突き付けた。
──
「あ、湊……すご…気持ちイイ湊……」
塞がりかけた傷をこじ開けるように、先生は僕の身体に硬くなったモノを突き立てる。
「せんせ…痛い……」
「すぐよくしてあげるから」
腰を動かされるたびに、内側を突かれるたびに、熱して溶けだした鉄の棒で内臓をほじくられているように感じた。目の奥で火花が散る。僕は先生が満足するまでの間、とにかく歯を食いしばって耐える外なかった。
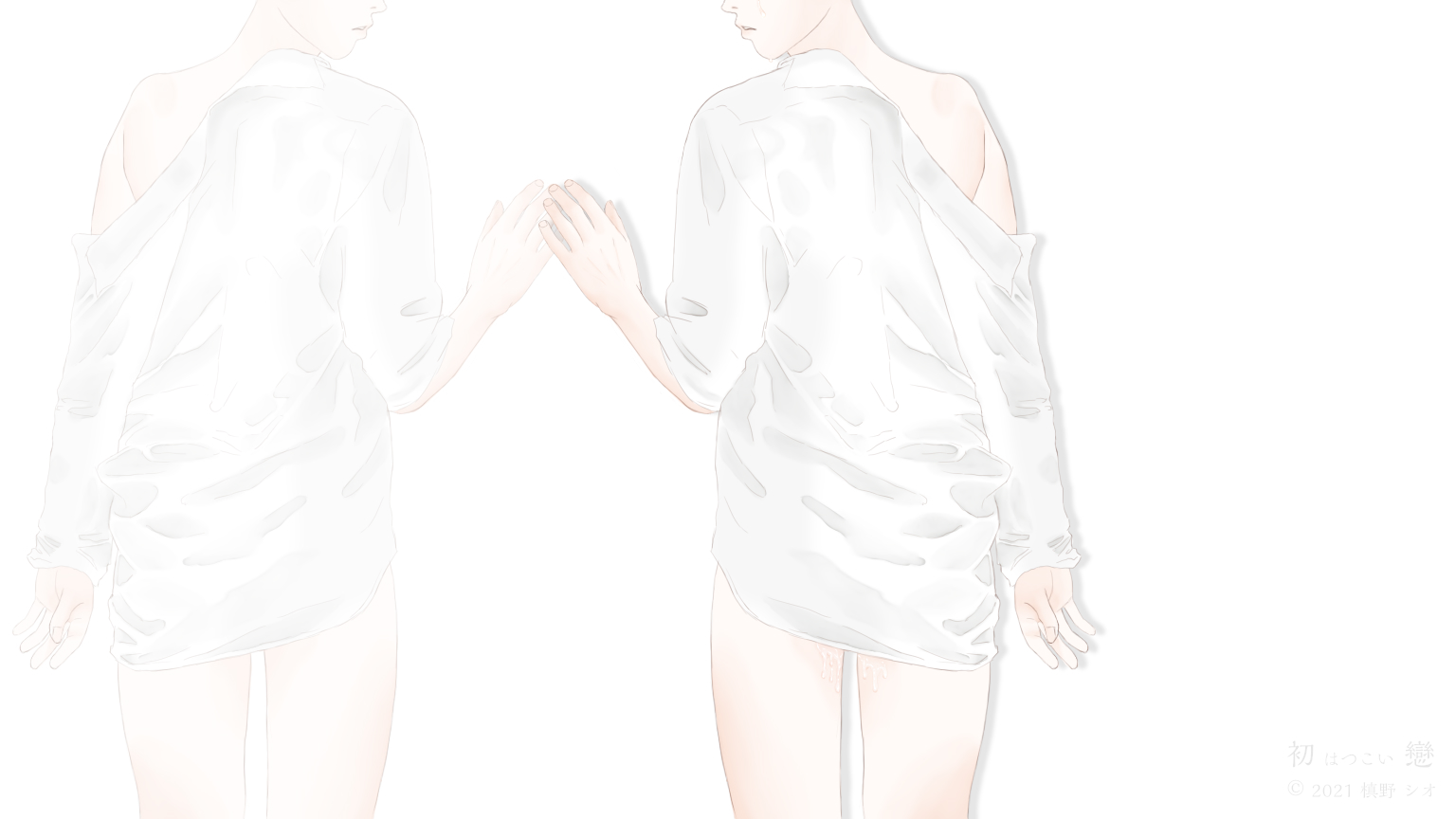
嫌がることも、ましてや抵抗することもできなかった。それは、先生のスマホの中に僕の “知られたくない姿” が収められているというだけではなく、あの日の僕を……小四の時、公園のトイレで快楽に身を委ねた僕を、先生だけはわかってくれるような、先生だけはそういう僕を排除しないような安心感があったからかもしれない。
なんでもいうことを聞くから、嫌いにならないで……
──
その日は委員会の仕事が長引いて、帰る頃にはすでに辺りは真っ暗になっていた。とにかく早く家に着きたかった僕は、普段通らない道を選択した。
学校の近くにある公園は中にトイレがあるくらいで遊具も何もなく、もっぱら住宅地へ向かうためのショートカットとして利用されていた。ただ、街頭のないその道を夜利用するひとはいなかった。
走れば大丈夫だ。
この公園に変質者が出ると連絡網で回って来たことは何度かあった。でもいまそんな話は聞いてないし、自分は男だから、という過信もあった。とにかく急いで駆け抜けよう。
そして、暗闇でもわかるほどの距離まで来て、目の前にひとが立っていることに気付いた僕は、それを避けて走り抜ければよかったものを足を止めてしまった。
いきなり襟を掴まれ引きずられるようにトイレに連れ込まれ、僕は何が起こっているのかすらわからなかった。ただ、とにかくその腕から逃れなくては、と必死でもがいた。そして掴まれていた手が放されたと同時に、腕に焼けるような痛みが走った。
「おとなしくしてないと手元が狂って、次は顔を傷付けちゃうかもなあ」
頬に触れる冷たい感触に身体が凍り付いた。
乱暴に髪を掴まれ、口の中にねじ込まれるソレに震えと吐き気が止まらなかった。助けて、助けて、助けて……抵抗したら本当に殺されるかもしれない、と恐怖で足が竦んだ。「脱げよ」と言われ、ベルトを外そうとするけど手が震えて上手く動かなかった。僕は壁に押し付けられ、何度か殴られた。
「…誰かいるのか? そこで何してんだ?」
物音に気付いた誰かがトイレを覗き声を掛けると、相手は僕を突き飛ばし走って逃げて行った。全身の震えを止めることができず、僕はその場にしゃがみ込み、嗚咽を漏らした。
「おい、大丈夫か?」
肩を揺すられ、大丈夫だと言おうとしたけどのどが痙攣して声が出ない。
「……湊?」
聞き覚えのある声に、いままでの恐怖が一気に溶け僕はそのまま気を失った。
──
「…大丈夫か、湊」
気付くと僕は知らない部屋で横になっていた。
「……先生」
「湊の家に行く途中だったんだけど……ビックリしたよ」
家教で僕の家に行く途中、いつものように公園を通り抜けようとして、何やら揉めているような物音に違和感を感じてトイレを覗き込んだ先生は、倒れた僕を病院に運んでくれたそうだ。
「腕、痛くないか? 五針縫ったって話だけど」
「少し…痛い…」
「顔は腫れてるけど、骨は折れてないって」
「ん……」
「もうすぐお母さん来てくれるから」
怖かった。何をされるのかわからなくて、どうなるのかわからなくて、殺されるんじゃないかと思って、本当に怖かった。先生が通り掛からなかったら、いまごろ僕はどうなっていたんだろう。切り付けられた腕と殴られた顔が痛くて、でもそれ以上に先生の存在に涙が止まらなかった。
「先生……」
先生、先生、先生、先生、先生……腕を伸ばす僕を先生は優しく抱き締め、「もう大丈夫だから」と頭をなでた。その瞬間、僕の世界で先生は絶対的なものとなった。
病院に来た母には、先生が説明をしてくれた。あくまでも通り魔的に怪我を負わされただけ、という話にしてくれたおかげで、母は怪我の具合以上の心配をすることはなかった。
それは後日、変質者が捕まり新聞に小さく記事が載ったことで、母を恐怖に陥れ神経質で過保護な性格を形成した。
──
先生との関係は、先生が大学四年生の秋になるまで続いた。かなり無理をしながらバイトを続けてくれていたけど、地元で就職が決まったという話で、割とあっさり離れた気がする。
「普通のフリしてないと、なかなか生きづらいからな」
先生の言った言葉が胸の奥に突き刺さったまま、抜けない棘のようにことある毎に鈍く痛む。
普通じゃない僕と先生は、普通じゃない行為を何度も何度も繰り返し、普通じゃない関係の中で傷を舐め合い自分自身を肯定しようと必死だった。気がする。
普通ってなんなんだろう。
答えはまだ見つからない。
***
「藤城……」
「うん」
「今日、なんでここに来た?」
「久御山とは違うって言ったの……誤解されたくなくて」
「……続き、しに来たって言えよ」
自己保身のために誰かを傷付けるようなことはしたくない。たとえそのことで自分が傷付いたとしても、自業自得だ。いまはまだ上手にできなくても、そのうちきっとそれが当たり前になる……そう思わなければ、今日ここに来た意味がない。久御山と友達になりたかったな。もう、遅いけど。
何もかもぶちまけて、これでよかったのかな、と思っていると久御山にシャツを脱がされ抱き上げられた。どういうつもりだよ、いまの話を聞いてなかったとでも言うのか。
久御山は僕をソファに座らせると、ベルトに手を掛けた。慌ててその手を押さえると、静かな声で久御山が言う。
「……硬いモノ欲しくて、脚開くんじゃないの?」
「何言って……」
「気持ちヨくしてあげるから……オレにもヤらせて」
「なんで……僕は…男なんだよ…?」
「……だから?」
だから、って……あっけなくベルトを外され強引にチノパンを剥ぎ取られ、僕は自分の身に起こっていることを理解するまでにしばらく時間を要した。久御山に腕を押さえられ、まったく歯が立たないことに情けなさを通り越して自分に怒りさえ込み上げて来る。結局僕は都合良く利用されるだけなのかよ。
「久御山…! なんでこんなこと」
「なんでって……好きなんでしょ? 気持ちイイこと」
「おまえ、相手に困ったりしてないだろ!? そんなにしたきゃ女の子に」
「いま、ここに、おまえがいるからだろ?」
「ふざけんな!」
久御山がただヤりたいだけだとは思えない……あれだけモテてるんだから、わざわざこんな労力を費やしてまで男を手籠めにする理由がない。でも……毛色の違う珍しいモノで遊びたいと思ってるとしたら? 力一杯身体を押してもびくともしないどころか、首筋を這う舌に気が遠くなる…
「やめろ、久御山……!」
「気持ちヨくなったら受け入れるんでしょ?」
「いい加減にしろよ!」
「おとなしくしてろって……すぐヨくしてあげるから」
「放せって! やめろって言ってんだろ!」
「されたんじゃなくて……したんだろ?」
「違う…!!」
「……使えねえ調教師だな……まだこんなに抵抗するじゃん」
……使えねえ調教師って……もしかして……
肩を支え起こしてくれる久御山の手が優しくて思わず顔を確かめた。いつもの飄々と自信に満ちた笑顔は鳴りを潜め、なんだか物悲しい雰囲気さえ漂わせながら、久御山は僕を抱き締めた。
「調教済みだなんて、とんだガセネタじゃねえか」
「…久御山……?」
「おまえに悪いところなんてないよ」
「……でも…」
「違うんだろ?」
「だって…それは……」
「おまえは悪くない」
「…久御山……」
…おまえはどこまで格好いいんだよ……どうして僕なんかのためにそこまでしてくれるんだよ……おまえが誘ったんだって、おまえが望んだんだって言われて、それを否定したところで何も変わらないって思ってたから……いっそ僕はそういう人間なんだって割り切れば、期待できない理由になると思ってたから……
「硬いモノじゃなくて」
「…えっ…うん…」
「オレが欲しくて脚開くように」
「…うん?」
「オレが調教し直してやるよ」
どこまで本気なのかわからなかったけど、久御山のドヤ顔に心が軽くなった。

