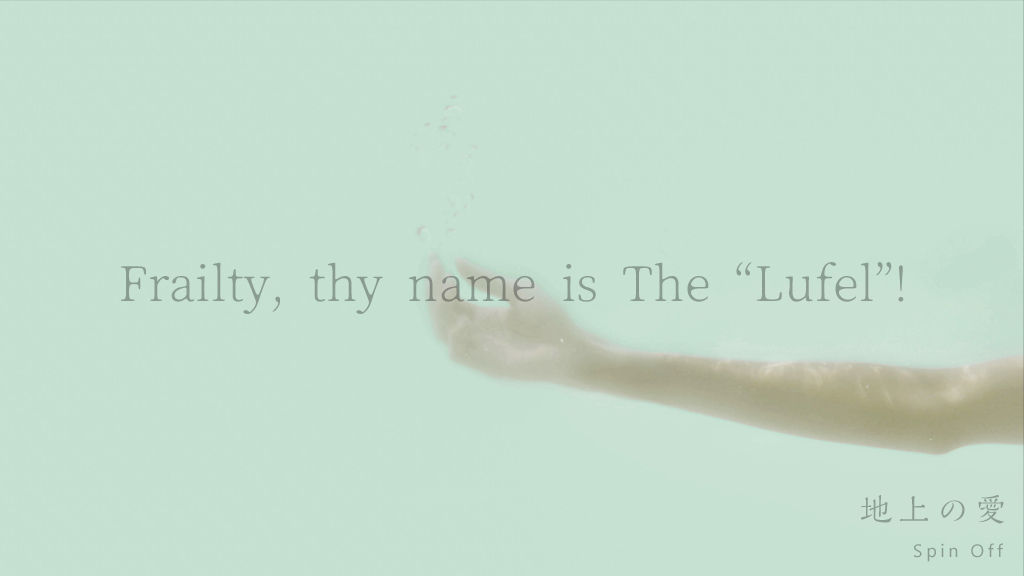Frailty, thy name is The “Lufel”!
scene.1 庭師の災難
自室で本を読みながら午後のうららかさにまどろんでいたところへ、けたたましくドアをノックする音が響き、しばしの休息を台無しにされたルフェルは不機嫌な声でその無礼者の入室を許した。
「……なんだ」
「大変申し訳ございません……しかしもう大天使長さまにお縋りするほかない状況でして」
「だから、なんだ」
「いますぐ庭園へとお越しいただきたく」
「……わたしを庭師か何かだとでも思っているのか」
「ミシャさまとフィールさまが……」
……また、あのふたりか。
───
重い腰をあげ、ルフェルは仕方なくエデンの南にある庭園へと向かった。
その庭園は小さいながらも手入れが行き届いており、さまざまな花が色とりどりの美しい花姿を並べ、庭を横切る小川や水車が情緒ある佇まいで見る者を癒し和ませている。その美しい光景に似つかわしいとは思えない斬撃音を轟かせ、ふたりの天使が争っていた。
ゆっくりと近付いて来るルフェルの姿に気付いたふたりは慌てて剣を収め、ばつの悪い顔でお互いの距離を取った。
「もう終いか」
低く静かな声でルフェルがふたりに声を掛けると、憤懣やるかたない様子で口火を切ったのはミシャだった。
「だってルフェル、フィールがわたしの天使たちを断りもなく勝手に戦闘に駆り出したのよ!」
「だから何度も言っているように、許可を取っている暇などない状況だったと」
「そんなの、伝令の天使にでも言付ければいいだけの話じゃない!」
「都合よく伝令の天使が隣にいるわけがないでしょう!?」
ルフェルは右手で空を切ると、その手に焔火で鍛えられ深紅に染まった熾烈の剣を納め、それをひと払いして剣身に溶熱した焔火をまとわせた。焔火は唸りながら剣身を包むと、不規則な火の粉を躍らせながら獲物を燃え尽くさんと待ち構えている。
「わたしが相手になろう」
……勝てるはずがないのは誰の目から見ても明らかだった。
「おまえたちは少々血の気が多いようだな」
「わたしの天使たちが傷付いたらどうしてくれるの!?」
「だから! 傷付いてもすぐわたしが治療できると何度言えば」
「……少々、ではないようだ」
ルフェルはふたりに背を向けると、「……許せよ」とつぶやき、右手に握った熾烈の剣を自身の正面で縦に振り抜いた。
「まだ言いたいことがあるなら聞こう」
ふたりを振り返りルフェルが言うと、硬直したまま「ございません」とフィールが冷や汗を流し、ミシャは唖然とした顔で立ち尽くすことしかできなくなった。
「あまり周りの手を煩わせるなよ」
そう言って、ルフェルは右手を開き握っていた剣を解放すると、また自室へと戻って行った。
「……一番周りの手を煩わせてるのって」
「言わないで、ミシャ……このあとのことを考えると胸が痛むわ……」
小さいながらも手入れの行き届いた庭園は、さまざまな花が色とりどりの美しい花姿を並べていたが、ルフェルの振り抜いた熾烈の剣が放つ斬撃波により、ちょうど中央で分断されたように焼けただれた道が一本できていた。庭園の三分の一ほどにもなるその道は、煙をくすぶらせながらそれまで咲き誇っていた花も、背の低い植え込みも、きれいに揃えられた芝も、一瞬で手放し荒れた焦土と化していた。
───
「いくらなんでもあれはないと思うの!」
自室で本を読みながら午後のうららかさにまどろむ暇もなく、けたたましくがなり立てしばしの休息をわざわざ台無しにするために来たとしか思えない訪問者に、ルフェルはうんざりしていた。
「大体あなたには情緒ってものがなさ過ぎるのよ!」
「……情緒」
「庭師たちが毎日心を込めて作っていた庭園なのよ!」
「……心を」
「それを一瞬で消し炭にしちゃうなんて、あまりにも酷いじゃない!」
「……酷い」
「どうするのよ、あの庭園! 責任取って元に戻しなさいよ!」
「……責任」
広げたままの読み掛けの本を、もう読んでいられる状況ではないとあきらめ、ルフェルは溜息を吐きながらぱたりと閉じた。それから背後で喚き自分を責め続ける声に、耳を塞ぎたいと思いながらゆっくり振り返って向かい合うと、もう一度深く溜息を吐いてから訊ねた。
「きみに情緒があって庭師を思いやる心があるのなら、庭園で斬撃音を轟かせるような酷いことはしないと思うし、手の施しようがないと僕に泣き付いて来る者もいなかったと思うんだけど、違うかい?」
「……何よ、わたしのせいだって言ってるの!?」
「きみのせいだとは言ってないよ、まだ」
「わたしにまったく責任がないとは思わないけど、消し炭にしたのはルフェルじゃない!」
「それは否定しないよ」
「だったら責任取って元に戻しなさいよ!」
「……ミシャ、僕は庭師でも、ましてや魔法使いでもないんだ」
「そうね、それならどうして取り返しの付かないようなことするの?」
じゃあどうして取り返しの付かないようなことをさせるようなことをするのか、と訊こうとしてルフェルはのど元でその言葉を留めた。言えば間違いなく火に油を注ぐ結果になるだろう。それはそれ、これはこれ、だ。たとえきっかけを作ったのがミシャとフィールだったとしても、焼き払ったのは僕自身だ。ミシャの言い分に間違いはない。
「……わかったよ。どうすればいいか教えてくれるかい?」
「とりあえず、謝りに行きましょう」
……謝りに。
───
ルフェルとミシャ、そしてフィールは庭園で茫然と立ち尽くす庭師に、どう話を切り出そうかと思案していた。
「あの……ミシャ、わたしたちはいいと思うんだけど」
「思うんだけど、何?」
「大天使長さまが……その……謝られるというのは……」
「焼け野原にしたのはルフェルなのよ? 本人が謝るべきでしょう?」
「いえ、その……お立場というものがあるから……」
「何よ、身分が高ければ謝る必要なんかないって言うの?」
「違うわよ……そうじゃなくて」
「ほらルフェル、行きなさいよ」
「ちょ、ミシャ!」
ミシャに背中を押されたルフェルは、そのまま真っ直ぐ庭師のそばまで行くと、十二枚の翼をでき得る限り小さく縮め、その足元にひざまずいた。
「ちょっと、ミシャ! あなた大天使長さまに一体何言ったのよ!」
「……わたしは謝りに行きましょう、って言っただけなんだけど」
「じゃあなんであんな最上級の謝罪をされてるのよ!」
「し、知らないわよ……わたしだって驚いてるんだから……」
庭の手入れにやって来た庭師が、三分の一ほど焼け野原になっている庭園を見て茫然としているところへ、大天使長である特級の熾天使が現れ、その背に輝く真っ白な十二枚の翼を窮屈そうに縮めながら突然にひざまずく姿を見て慌てないはずがなかった。当たり前のように庭師は腰を抜かしそうなほど驚き、委縮してしまっている。
しかもこの階級主義のエデンにおいて、上級の天使が下級の天使にひざまずくなどということはまずもって考えられず、さらに言えば庭園の庭師は現役を退いて久しい “階級を持たない天使” だったことから、自分にひざまずくような地位の天使がいるなどとは思わず、突然の出来事にただただ慌てふためくことしかできない。
「ど、ど、どうなさったのですか大天使長さま!」
「大切に育て手入れをする美しい庭を荒らし大変申し訳ない」
「……え? ……庭?」
「ついては以前の姿を取り戻すために必要なことを知りたいのだが」
「と、とんでもないことでございます……」
「何かわたしにできることがあれば」
「い、いえ、あの、滅相もないことでございます……」
そこにミシャとフィールが申し訳なさそうな顔で現れ、そもそもふたりが原因を作ってしまったのだと庭師に頭を下げた。庭師にしてみればミシャもフィールも上級天使であることに変わりはなく、あり得ないことが続けざまに起こることが恐ろしくて、庭の心配より自身の心配をしたほうがいいのではないかと縮み上がるばかりだった。
しかし目の前でひざまずき、また頭を下げる上級天使たちが、庭園を荒らしてしまったことを本心から詫びているのだと知り安心した庭師は、造園のことを仕事として請け負っているわけではなく、余生の楽しみのようなものだと話し、また新しい草花を育てられることは喜ばしいことだと微笑んだ。
「ミシャ……だから言ったじゃない……」
「今回ばかりはわたしが間違ってたと思ったわ……」
「大天使長さまが謝られるというのはこういうことなのよ」
「……あんなに縮こまってしまうとは思わなくて……」
───
自室で本を読みながらせめて夜は静かに過ごしたいと思っているところへ、しおらしく肩を落としたミシャが現れ何も言わず目の前で膝を抱えたままでいることに、ルフェルは困り果てその理由を訊ねた。
「何か言いたいことがあるからここへ来たんじゃないのかい?」
「…………」
「……ミシャ、僕は庭師でも、ましてや魔法使いでも、あえて加えるなら超能力者でもないんだ」
「……うして」
「ちゃんと言葉にしてくれないとわからないことのほうが多いんだよ」
「どうして普通に、じゃなくて最上級の謝罪をしたの?」
「……謝るのに普通も何もないだろう?」
「庭師……あんなに縮こまっちゃったじゃない……」
「いや、それは……僕がどうこうできるものではな」「庭師に申し訳ないことしちゃったわ……」
…………庭師たちが心を込めて作っている庭園を、一瞬で消し炭にする酷い振舞いは情緒がなさ過ぎると詰られ、責任を取って元に戻せと、とりあえず謝れと叱責され、反省して謝れば謝ったで相手を委縮させたと咎められる……ルフェルはこの理不尽な扱いにめまいすら覚えながら、二度とこのふたりの喧嘩にだけは関わるまいと心に誓った。