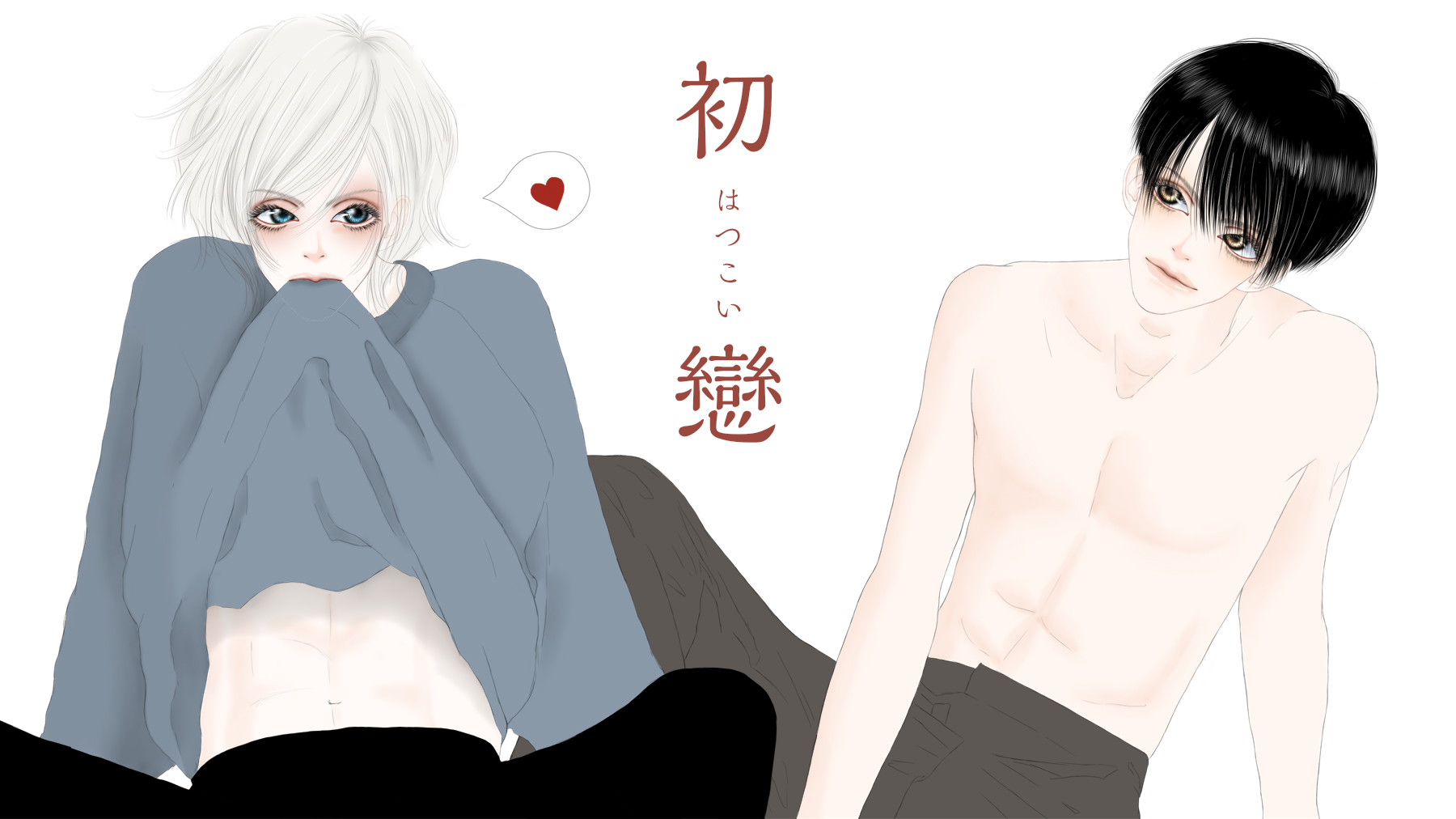第七十五話 火を避けて水に陥る
十七年と半年生きて来て、まさか自分が「結婚」を意識する日が来るとは思ってなかった。決して恋愛を馬鹿にしてたわけじゃないし、世の中には結婚という選択があることも知ってはいたけど、そういうことから一番遠いところで生息してる自覚があった。
毎日面倒なく過ごせればいいじゃん、何かに執着して傷付く必要なんてないじゃん、楽しければいいし気持ち良けりゃいい。そういう生き方しかできないと思ってたし、それが不幸だと思ったこともなかった。
── 湊を知るまでは。
「…っ…はあっ…あ、あ、あ…も…イく…」
「まだダメ…もう少し可愛がって」
「けんそ…も、無理……っ…う…ん」
「エロい顔しやがって」
握り締めていたシーツから指が離れ、湊がオレに両腕を伸ばす。カラダを倒して覆いかぶさると、オレの首に腕を絡める。最近、イくときにキスをねだるようになった。部屋が明るくてもカラダを隠さなくなった。必死に声を抑えようとしなくなった。どこを吮めても拒絶しなくなった。
顔を赤くしているところをみると、慣れたわけでも恥じらいを失くしたわけでもなく、ただオレのすべてを受け入れようとしてくれているのがわかる。他の誰にも見せない姿を、他の誰も知らない湊を、オレにだけ与えてくれる。
「……オレさあ」
「ん……?」
「肩書きとか記念日とか贔屓目とか特別扱いとか、そういうのまったく気にしたことなくてさ」
「う、うん……突然どうした…」
「家族も親族も地元のツレもみんな名前で呼ぶからさ、特にこだわりなかったのよ」
「うん」
「東京だとみんな名字で呼ぶしさ」
「ああ、そうだね」
「でも、やっぱ違うわ……湊に名前呼ばれるとゾクゾクするしキュンと来る」
「えっ……そんな風に言われたらまた意識して呼べなくなるじゃん!」
「オレって実は乙女だったんだなあ、って……最近よく思う」
「デカい乙女だな…」
「もう受験より湊の紋付袴姿が気になって仕方ない」
「おまえはいいよ……僕は追い込み掛けないとそろそろヤバい」
「……湊、勉強すんの?」
「当たり前だろ、僕には一度目を通しただけで内容を丸暗記できるような能力はない」
「じゃあ、あとで一緒に勉強しよ」
「ん、しばらく休憩したい?」
「ううん、もう一回ヤりたい」
「待ちたまえ」
「あっ、はあっ……みなとぉ…んんっ…」
「どうした? もう一回ヤりたかったんだろ?」
いや、間違いではないけどオレが攻められるのは想定してなかった……あっ…うう…これはこれですごくイイんだけど、主導権を握られ有無を言わさずヨくされてしまうと…あぅ…
「そ…だけど……んっ…そろそろ挿れてよ……焦らし過ぎ…」
「焦らしてるんじゃなくて、慣らしてるんだよ」
「も…大丈夫だから……湊…」
そして、最近気付いたことがある。
二年間ずっと攻めだったし、湊も挿入したことがないって言ってたから、まさか自分が受けになる日が来るとは思ってなかったけど、ネコになってみるとこれがまあ……
── 湊がカッコイイ…
オレの脚を抱えて腰を動かしてる姿もさることながら、こめかみから流れあごから滴り落ちる汗も、眉間に寄せるシワも、どんどん荒くなる息遣いも、時々漏れる低く掠れた声も、ぎゅっと目を閉じて我慢してるところも、もう何もかもが雄っぽさ全開でキュンキュン来る。イく瞬間にオレの名前を呼ぶところなんて、もはや殺しに来てんのかとさえ思う。
「あ、あ、あ、あ、あ…ゴリゴリ当た…っ…ふ…あ…」
「あんまり締めないで……」
「…んなこと言われても…あ、あ、あ…っ…湊ぉ…内臓潰れ…る…」
「しんどい?」
「イイ…飛びそ……気持ちくて飛ぶ…」
ただひとつ、不満があるとするなら ──
「……飛ん…だ…」
「ん、もう大丈夫? しんどくない?」
湊が少し心配そうな顔でオレの目を覗き込む。
「大丈夫…だけど……」
「だけど? どうした?」
「湊、イってなくない?」
「ああ、うん……なんだよ、そんなこと気にしてるのか」
「気にするだろ!? え、なんで!? イかなくていいの!?」
「んー……なんか、賢颯の良さそうな顔見たら満足しちゃった」
「もしかして、オレあんまりヨくない!?」
「何言ってんだバカ」
「だってオレ、挿入しててイかないなんてこと絶対ないもん!」
「力説するようなことでもないぞ…」
時々こうして湊は平然とした顔をする。体調が悪いとか悩み事があるとか、ましてや何か不満があるとかってわけではなさそうだけど、セックスでイけないって死活問題では!? 否定したけどやっぱりオレのカラダがヨくないとか!?
……ヨくなかったとして「おまえのユルい穴じゃイけないんだよ」なんて、面と向かって言うわけないわな。さすがにオレだって、あんまり具合のよろしくない女の子相手にそんな鬼畜なこと言ったことないし。
でも、される側だとちゃんとイくんだよな、湊……それこそ何か不満があるようには見えないというか……むしろ理性も知性もすっ飛ばして、いやらしさ全開で腰くねらせながら鳴いてるの見てると、どんだけイイんだよチクショー可愛いな! って、もっとヨがらせてやりたくなるくらいエロく……いかん、思い出して勃たせてる場合じゃねえ。
セックスレスが離婚の原因になったりする世の中において、セックスってやっぱすげえ大事なんじゃないの?
とはいえ、こんなこと誰にも相談できないというか、相談しても問題なさそうな相手が思い付かない。沓川、一ノ瀬、嵩澤……は絶対ないな……宗弥さん、桜庭、橘さん、綾ちゃん、シロクロ、桐嶋……真壁さん…うーん……バーのマスターとか…似たような立場の人間となると、やっぱり宗弥さんになるんだけど…
甥っ子の下の話なんて相談されても困るだろうし。
───
「悪い、予想以上に遅くなった」
「いえ、こちらこそ仕事中にすみません」
「いい気分転換になるよ」
結局考えた末に宗弥さんを召喚してしまった。さすがにファミレスやマクドに呼び付けるのはどうかと思い、小洒落たカフェをチョイスしてしまったオレはいま、激しく後悔していた。
入口で店員に声を掛けられ、店内をさっと見渡してオレに気付いた宗弥さんは、店員に会釈をすると足早に歩いて来る。少し慌ててる姿さえ格好いい。「悪い、予想以上に遅くなった」と言いながら上着を脱いで腰をおろし、「いい気分転換になるよ」とネクタイを緩め微笑む。
さっとメニューを見ながら、オーダーを取りに来た店員を待たせることなくスマートにカプチーノを頼み、笑顔までサービスする宗弥さんの洗練された振る舞い。どういう時間を過ごせばこんな格好いい男になれるんだ。
そしてオレはいまからこのひとに、こんな洒落た場所でシモの相談をしようというのか。
「それで、相談って?」
「……するつもりでしたが、気が引けてしまいました」
「なんでだよ」
宗弥さんは、いまさら遠慮する仲でもないだろ、と笑ってオレを促した。
「なんていうか…こんな話をこんな格好いいひとにするのもなあ、と…」
「ゲスい話はむしろ得意分野だよ」
「ゲス過ぎてオレが躊躇するくらいです」
「何よ、湊と上手く行ってないの?」
「いえ、揉めてるわけでもないんですが」
「あっちの話?」
「……ええ…まあ…」
さすがに剛の者だけあって鋭い。わざわざ仕事の合間に抜け出して来てくれたんだから、話さないのも却って失礼かもなあ、と意を決して重い口を割った。
「宗弥さん、イかないことってあります?」
「ないな」
「終ー了ー……即答だった」
「賢颯くん、イけないの?」
「いえ、逆で」
「えーと、それはどういう状況で?」
「……オレが受けの場合、ですけど」
途中、カプチーノを運んで来た店員の前で無言になりながらも、なるべく下品にならないよう心掛け「湊がウケだとイくのにタチだとイかないのはどうして!?」というアホな悩みを相談してみた。
「うーん……あ、過去に似たような経験あるわ」
「桜庭で?」
「いや、相手は女の子だけどさ……痛いって言われたことがあって」
「ああ、そういうのはオレもありますけど」
「相性もあるんだろうけど、奥まで挿れると痛いのかなあと思って結構セーブしたんだよ」
「……もしかして、それが原因…?」
「イイかどうかより、痛いかどうかが気になっちゃってさ」
「結局どうしたんですか?」
「すぐ音信不通になったかなあ」
「不吉なこと言わんでください…」
「気になって手加減してるのかもしれないな」
「…手加減……されてるのか…」
確かに、根元まで挿れなくてもイけるけど、別のことが気になってしまうと達し難くなるかもしれない。以前湊と話をした時に「将来的には勝ち組じゃん」みたいなことを言った気がするけど、全然勝たせてあげられてないのでは!?
「やっぱ男の子は我慢ですかね…」
「……思ってるより深刻そうだね」
「飽きられたり嫌われたりしたくないなあ、とか」
「多分湊も同じこと思ってるんじゃない?」
「……たかがセックスって思ってたんですけどね」
「自分に正直に、相手には素直に……上手く行く裏技なんてないからね」
カプチーノを飲み干し宗弥さんは、「俺が恋と向き合ったのは、三十二になってからだよ」と眉を下げながら頼りなく笑った。
───
「あの、ちょっとよろしいですか?」
宗弥さんと別れ駅に向かって歩いていると、突然見知らぬひとに呼び止められた。明らかにナンパではなさそうな出で立ちだけど、キャッチにしてはまだ時間が早過ぎる。しかも相手は女性だ。
「二十歳前後の女性をターゲットにしたファッション誌で、毎号街で見掛けたおしゃれさんのスナップを掲載してるんです。よろしければ……って、あの! 憶えてませんか!?」
「……以前声を掛けられたことがあるような」
「そうですそうです! ずっと探してたんですよ!」
「は? オレを? なんでまた……」
相手の女性は興奮気味に頬を紅潮させながら、早口で話し始めた。
── 今度、メンズのファッション誌を創刊することになったんですが、アイテムの紹介や特集記事だけじゃなく、読者との距離感を縮める企画としまして、素人さんを発掘しその男の子が磨かれ輝いて行くまでの軌跡を毎号追って行き、磨かれた暁にはプロとして活躍できる場を提供する、という……原石を探してるんです。
初回はある程度レベルの高い子のほうがいい、という話になっていまして、何人かもうお話させていただいてる子はいるんですが、きみが一番レベルが高く一番格好いいので……ずっと逢えないかなと思ってたんです。
「読者モデルみたいな感じ?」
「若干異なりますが、モデル事務所と契約していない素人さんという点では似たようなものです」
「なるほど、でもオレ受験生だから」
「あの、時間はどれだけでも融通効きますし、もちろんギャラも出ますんで!」
「……ギャラ、出るんだ」
「はい、出ます! 読者モデルだと五千円前後ですが、今回の企画は一回の撮影で二万から三万は出ます!」
「月に何回くらい撮影あんの?」
「打ち合わせの日も合わせて、五日から八日くらいです」
……いまのバイトが時給千五百円で一日五時間、週三日で考えると一か月で九万円。まあ残業とか土日を考えると毎月十二万円前後にはなるけど……稼働日数が十二日から十五日。それに引き替え五日から八日で十万円から最高二十四万円って考えると、そりゃそっちのほうが時間の節約にはなるよなあ。
「少し考えてみてはいただけないでしょうか!」
「うん、じゃあ連絡先教えてくれる?」
「はいっ、ありがとうございます! あ、これ名刺です!」
まあ、宗弥さんと桜庭が載ってた雑誌は見たし、怪しいスカウトじゃないのは確かだろうけど。いまのバイト先にはすげえ世話になってるし、とはいえ湊と一緒にいる時間が増えることを思うとなあ……
───
「モデルのバイト?」
「うん、どう思う?」
家に帰ると、湊がリビングのテーブルで参考書と問題集を広げ、床に教科書や辞書を積み上げ受験勉強をしていた。わざわざオレの家で勉強しながら待っててくれるところが湊らしい。
「へえ、面白そうだね……ものすごい天職だと思うけど」
「まあ、プロになる気はないから磨いてもらってハイお終い、だけどなあ」
「それ以上どこを磨くんだ、って気はするけどね」
「労働時間が減れば一緒にいられる時間も増えるし…」
「僕、受験勉強で賢颯に構ってる暇ないかもよ?」
「それでも、同じ空間にいるのといないのじゃ全然違うんだよ」
「それな……隣にいてくれるだけで勉強捗るもんなあ」
「可愛いかよ!」
もらった名刺を見ながら電話を掛け、一度撮影の見学をさせてもらえないか、と頼んでみたら快諾してくれた。高校生相手になんて心の広い出版社なんだろう。
実はこういうスカウトは初めてじゃない。ただ、見た目でチヤホヤされても先が見えてるというか、勝手に期待されて思い込みで落胆されることに疲れていたせいで、華やかな世界にまるで興味が持てなかったんだよなあ。いまもモデルの世界に興味はないけど、湊との時間には代えられない。
───
日曜日、湊と一緒に渋谷にある撮影スタジオへと足を運んだ。RC造がお洒落な建物をふたりで見上げ、撮影する場所までお洒落なんだねえ、と小学生並みの感想を漏らしながら中へ入った。
受付カウンターの前にいた女性が振り返り、笑顔を弾けさせながら走り寄って来る。
「連絡ありがとうございます! あ、こちらが電話で言っていたお友達ですね? はじめまして、奏成社の吉村です」
「あ、はじめまして、藤城と申します」
「藤城くんも背が高くて格好いいですね……第二弾は藤城くんにお願いしようかな…」
「いえいえ、僕にそんな大役は…」
いま休憩中なのでスタジオの中は自由に見てもらって大丈夫ですよ、と吉村さんはスタジオの扉を開けた。いろんな機材が置いてある場所を自由にウロウロできるほどの注意力なんかねえわ、と思いながら扉を背にスタジオを見渡す。壁が真っ白でなんだか落ち着かない。
やっぱりオレと湊は「すごいなあ」と小学生並みの感想を漏らすことしかできなかったが、この世界に興味のあるひとならきっと大はしゃぎに違いないシチュエーションなんだろう。
撮影しているところを見せてもらうために、休憩が終わるまでロビーで待機していると、建物の入口が賑やかになった。撮影班が戻って来たのかなあ、と振り返るといかにもそれらしい集団がロビーを横切って行く。
じゃあ行きましょうか、と吉村さんに言われソファから立ち上がったオレの脚に何かがトンっとぶつかった。なんだろう? と俯くと、小さな……二歳か三歳か、とにかく幼児が脚にしがみ着いていた。
「……スタッフの子? まさか迷子じゃ」
「パパ!」
── パパ?
「……悪いけど、ひと違いじゃないかな…」
「パパだ!」
オレの脚にしがみ着く幼児の横で湊は腰を屈め、何も言わずに幼児の小さな頭をなでた。