第四話 籠鳥雲を恋う
「賢颯、何もそこまでしやんでも……」
「ぼくがそうしたいだけやから……気ぃ遣わんとって」
「ほんまに大丈夫なん? 最初だけでも一緒に」
「いや大丈夫やから……ほなもう行くわ」
「たまに帰って来てよ」
「うん、わかってる」
最低でも一年に一回は……嫌でも顔見なあかんやろ。
バス停でぼんやりしていると誰かに名前を呼ばれ、振り返るとこっちに向かって走って来る影が見えた。
「賢颯!」
「…華……どしたん」
「どしたんちゃうわ、なんで黙って行こうとするん?」
「や、出るときいてへんかったやん」
「そやけどLINEでもなんでもあるやん!」
「ああ、まあ……そやな」
「約束して、賢颯」
「何?」
「毎日一回LINEして」
「あほか……なんでそんなめんどいこと」
「おらんようなるんちゃうかって……不安やもん……」
「……大丈夫やって……何の心配やねん」
引っ越したばかりで何かと大変だろう、と母はしばらく東京にいると言った。
兄離れできない妹は一日一回LINEをしろと無茶を言った。
ぼくは……鴨川にすべてを流してなかったことにした。
いい思い出なんて何ひとつないこんな場所でも、最後の別れを告げると途端に懐かしい生まれ故郷に変わる……なんてことはまったくなかった。
***
夜遅くインターホンが鳴る。
いま何時だ……もう宅配便とか届く時間じゃないよな……こんな時間に訪ねて来るツレなんてこっちには……
「…はい」
「あ、あの……藤城…です…」
「なんか用?」
「……今日…ごめん」
「うん……いいよ、もう」
「…ん……それだけ……」
プツン、とインターホンが切れた。
もう電車もバスも動いてる時間じゃないだろ……
「…藤城っ」
「……久御山」
「なにやってんだよ……歩いて帰るつもりか」
「う、うん……」
「馬鹿か、襲われたらどうすんだ」
「……っ」
「来いよ」
藤城は俯いたまま、玄関から動かなかった。
「入れよ」
「ここでいいから……踏み込んだりしないから、少し話を…」
「逆に気遣うから入れって」
渡した麦茶のグラスを握り締めたまま、藤城は一所懸命言葉を選んでいるようだった。藤城はおとなしいやつではあったけど、こんなにおどおどと落ち着かない様子を見せるのは初めてだった。
「僕……僕は…あの……」
「ゆっくりでいいよ……急がないし、別に言葉選ばなくてもいいし」
「……女の子を…………好きになれないんだ…」
「うん」
「……えっ」
「うん、だから?」
「き…気持ち悪く……ないの…?」
「なんで気持ち悪いの?」
「だって……」
「……だったら、おまえに尺られてイったオレも充分気持ち悪いだろ」
「久御山は格好いいじゃん……」
笑ってしまった……いま格好いいとかそうじゃないとか、関係あったか?
「オレが格好良くてセーフなら、おまえも可愛くてセーフだろ」
「……可愛い男なんて……価値ないよ」
「価値があるかないか、決めるのは周りでしょ」
「変質者とか痴漢とかには……好かれるけど」
「ああ、まあ弱そうなやつのほうが狙われやすいかもね」
「……最初は…わかんなくて」
「何が」
「何されてるか……わかんなくて」
「…………」
「まだ小学生で、そういうこと知らなくて」
「藤城」
「誰にも……言えなくて…」
「藤城……無理に話さなくても」
「その時は……前…を触られたり…な、舐められたりしただけなんだけど」
それから藤城は絞り出すように言葉を続けた。小四の時変質者に遭ってから、母親と話せなくなったこと。中一の時家庭教師だった大学生に犯されたこと。その関係がしばらく続き ── 自分が同性愛者だと自覚したこと。それが周りにバレることが怖くて友達が作れなくなったこと。
「そのカテキョって、いまどこで何してんの」
「わかんない……多分大学は卒業してる……」
「……なんでおまえが割食ってんの」
「僕にも……悪いところがあったと思うから」
「どこに?」
「僕が……僕が誘ったって」
「何言ってんの」
「だから強姦じゃないって言われて、そうなんだって……」
「立派に犯罪だろうよ」
「でも……そのあと何度もしたから…」
「したんじゃねえ、されたんだろ!!」
オレを見上げる藤城の目が怯えていた。
床に座り膝を抱える藤城は弱々しく、いまにも消えてしまいそうなほどの儚さでやっと存在しているようだった。なぜか不安になって抱き締めると、藤城は警戒心をあらわに身体を強張らせた。
「……なんなんだよ」
「ご、ごめ……」
「その大学生はのうのうと生きてんのかよ……」
「で、でも、悪いひとではないっていうか」
「かばうな……ムカつく」
「っ…ごめん……」
「謝るな……自分が情けなくなる……」
「な……なんで…」
「……怖い?」
「え……なに」
「オレのこと、怖い?」
「久御山は……怖くない…けど…」
「けど?」
「自分に……絶望する……」
「なんで……」
答えに迷っているのか、それとも答えることを躊躇っているのか、藤城はしばらく無言のまま俯いて、それからゆっくり顔をあげてオレの目を覗き込んだ。
「されたんじゃなくて……したんだよ」
そう言って藤城は笑った。
「結局気持ち良くなって僕の身体は相手を受け入れる。そういう風に調教されてるんだ」
どんなに嫌だと思ってたって……僕の身体は簡単にその思いを裏切って貪欲に快感を求めるんだ。泣いても、叫んでも、何を言われても、何をされても、僕は……硬いモノが欲しくて脚を開く。そんな自分を知られたくなくて……でも……普通のフリも……上手にできなくて……
それなのに死ぬこともできない臆病者なんだ、と藤城はもう一度頼りなく笑った。
手も足も出なかった。
こういうとき、臨床心理士とかカウンセラーとかそういうひとたちはどんな言葉を掛けるんだろう。どう言えば不快なく癒すことができるんだろう。そもそも癒したいとか思い上がりも甚だしいな。オレは他人様を癒せるほど上等な人間じゃなかった。それでも……オレにできることって、何ひとつないんだろうか。
他人に憐れまれる居心地の悪さはオレが一番よくわかってる。対等な人間だと思ってないあの目付きに、少し安心したような、優越感さえ漂わせるあの視線に、幾度となく傷付き落胆し諦め……ああ、藤城はまだ諦め切れないんだな。だから未だに傷付いて、傷付きたくないと殻に閉じこもるんだ。
普通じゃないと気付かされたときの絶望感が、身体に纏わり着いて離れない。受け入れることも、開き直ることもできず、社会の枠組みから弾かれたまま……普通のフリを自分に科して息をひそめる。
「藤城……」
「うん」
「今日、なんでここに来た?」
「久御山とは違うって言ったの……誤解されたくなくて」
「……続き、しに来たって言えよ」
シャツを脱がせると両腕でカラダを抱え、まったく肉の付いてない白い肌を隠そうとする。抱き上げてソファに座らせ、ベルトに手を掛けると慌ててオレの手を押さえた。
「……硬いモノ欲しくて、脚開くんじゃないの?」
「何言って……」
「気持ちヨくしてあげるから……オレにもヤらせて」
「なんで……僕は…男なんだよ…?」
「……だから?」
ベルトを外しチノパンを脱がせると、藤城はカラダの向きを替えソファから逃げようともがいた。腕を押さえパンツに手を掛けるオレをなんとか振り切ろうと脚をバタ付かせ……あまりの力のなさに、驚きを通り越し悲しみさえ込み上げた。こんな簡単に自由にされてしまうのかよ……
「久御山…! なんでこんなこと」
「なんでって……好きなんでしょ? 気持ちイイこと」
「おまえ、相手に困ったりしてないだろ!? そんなにしたきゃ女の子に」
「いま、ここに、おまえがいるからだろ?」
「ふざけんな!」
ソファから転がり落ちて、藤城はキッチンに逃げ込んだ。そのままキッチンの冷えた床に押し倒しカラダにまたがると、歯を食いしばりながらオレの肩を押し返そうと足掻く。両腕を押さえ首筋に舌を這わせるオレの下で、なんとか自由にされまいと藤城がカラダをよじる。
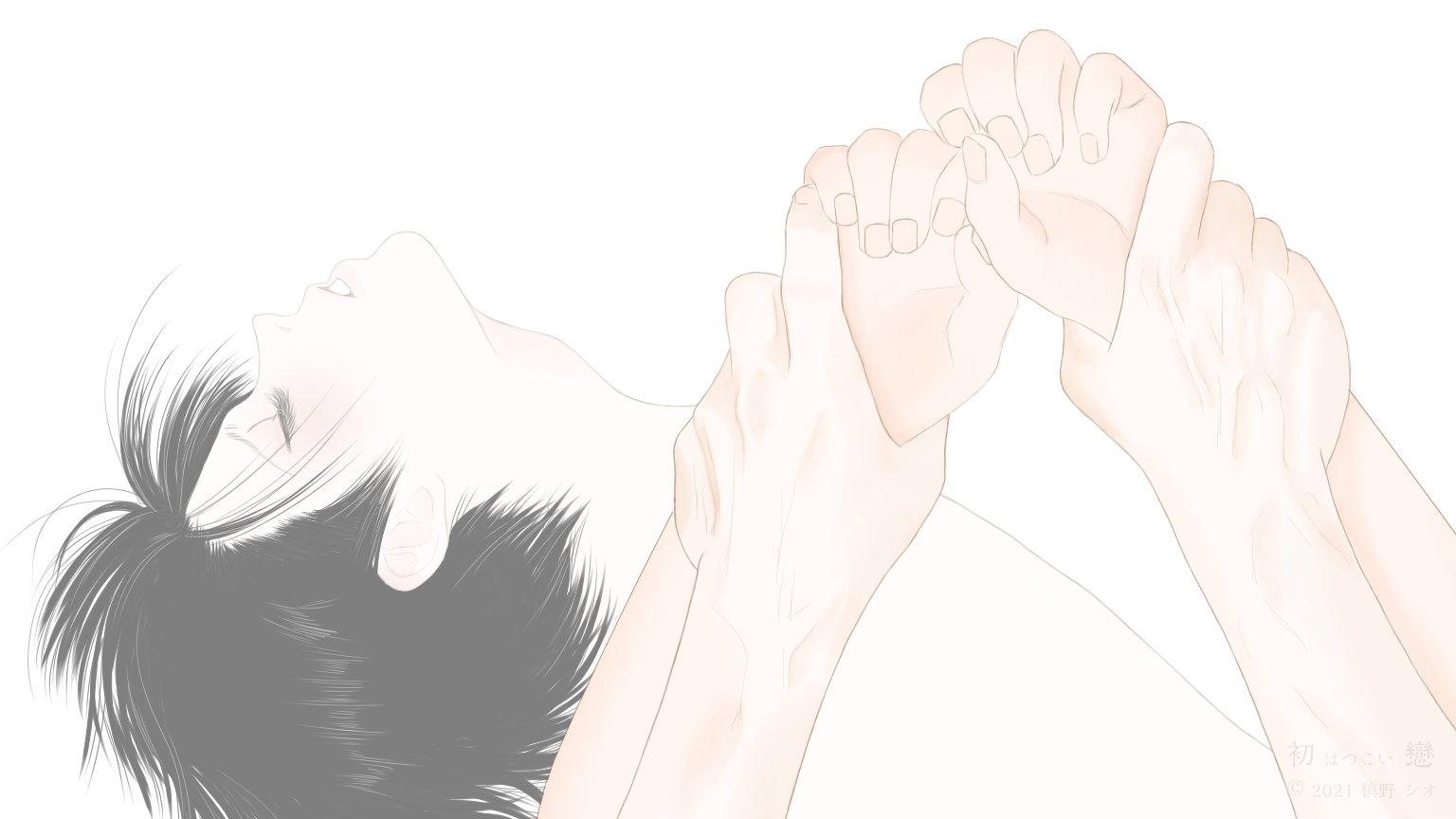
「やめろ、久御山……!」
「気持ちヨくなったら受け入れるんでしょ?」
「いい加減にしろよ!」
「おとなしくしてろって……すぐヨくしてあげるから」
「放せって! やめろって言ってんだろ!」
「されたんじゃなくて……したんだろ?」
「違う…!!」
「……使えねえ調教師だな……まだこんなに抵抗するじゃん」
身体を起こし、藤城の肩を支えながら腕を引っ張ると、想像以上に軽くてやっぱり悲しくなった。華奢な背中に腕を回し抱き締め、藤城が震えていることに自責の念で死にそうになる。
「調教済みだなんて、とんだガセネタじゃねえか」
「…久御山……?」
「おまえに悪いところなんてないよ」
「……でも…」
「違うんだろ?」
「だって…それは……」
「おまえは悪くない」
「…久御山……」
藤城はオレの首にしがみ着き、声をあげて泣き出した。大学生との交尾で同性愛者だと自覚したらしいけど……そういう自分をさらけ出せる唯一の相手が、自分を強姦した相手だっていうのも残酷な話だな……弱味を握られ、されるがままの自分を本当の自分だと思い込むくらいには……好き放題してたんだろうな、その大学生。
「硬いモノじゃなくて」
「…えっ…うん…」
「オレが欲しくて脚開くように」
「…うん?」
「オレが調教し直してやるよ」
藤城は泣きながら笑った。
「…藤城、昼間の続きしてもいい?」
「えっ…」
「いまは嫌だってんなら、待つから」
「あの……久御山、ノンケだよね…」
「うん、多分」
「だったら……女の子としたほうがいいんじゃないかな」
「おまえとしたいって気持ちが、他の女の子で満たされんの?」
「いや、なんで僕と…」
「納得できる理由がないと駄目?」
「僕は男で……同性愛者なんだよ…」
「だったら、オレも男だから問題なくね?」
裸体にした藤城は本当に細く、肌の白さも相まって滅茶苦茶きれいに見えた。細い首に顔を埋めると、シャンプーなのか香水なのか、柔らかい甘いにおいがした。首筋に舌を這わせ、藤城が漏らす吐息を確かめる。泣いていないことを知って、胸の奥に安心感が広がって行く。
首筋から鎖骨をなぞり、やたら敏感だった場所をそっと舌先で突つくと、細いカラダが大きく跳ねた。
「……そんなイイの? ここ」
「訊くな……あ、あ、あ、ちょっ……」
「乳首……ピンク色できれいだね」
「言うな……!」
自分の腕を噛んで声を抑えてる姿にドキッとする。ああ……こういう捨て身で必死なところが男心をくすぐるんだろうな……そう思ったら、大学生のことを思い出しこめかみに鈍い痛みが走った。
「藤城、腕噛まないで」
「あ……ん、ん…」
「目、閉じないで……」
噛んだりしないよう、腕を掴んで尖らせた乳首を舐めると、堪え切れなかった鳴き声が部屋に響く。
「いいよ、そんな壁薄くないから」
「…やだ…よ……あ、あ、あ……う…っ…あ」
「ほら、目閉じないの」
ここまでは相手が女の子でも変わらない。問題はこの先で、さっきから腹に当たってる硬いモノをオレは舐めたり咥えたりしたことが、ない。当然と言えば当然で、もし藤城に出逢ってなければ一生そんな経験はしなかったかもしれない。身体を下にずらし、その硬いモノを……
白く細いカラダには、そのカラダにも可愛い顔にも到底似合わないモノが付いていた。
当然男のナニを咥えるのは初めてなわけで、正直このサイズのモノをどう扱っていいのかわからなかった。
「……どうしたらイイか教えて」
「…久御山に……そんなことさせたくない」
「他の男ならいいの?」
「違う……!!」
「じゃあ教えて」
「僕……汚れてるって…汚いって言われて、だから久御山を汚したくな」
「だったら尚更教えてよ。オレを汚してお揃いになろうぜ」
「久御山……」
「汚してよ……ふたりで汚れて堕ちればいいじゃん」
粘膜擦り合わせたくらいで汚れるような、そんな安いカラダ持って産まれたヤツなんかいねえよ。

