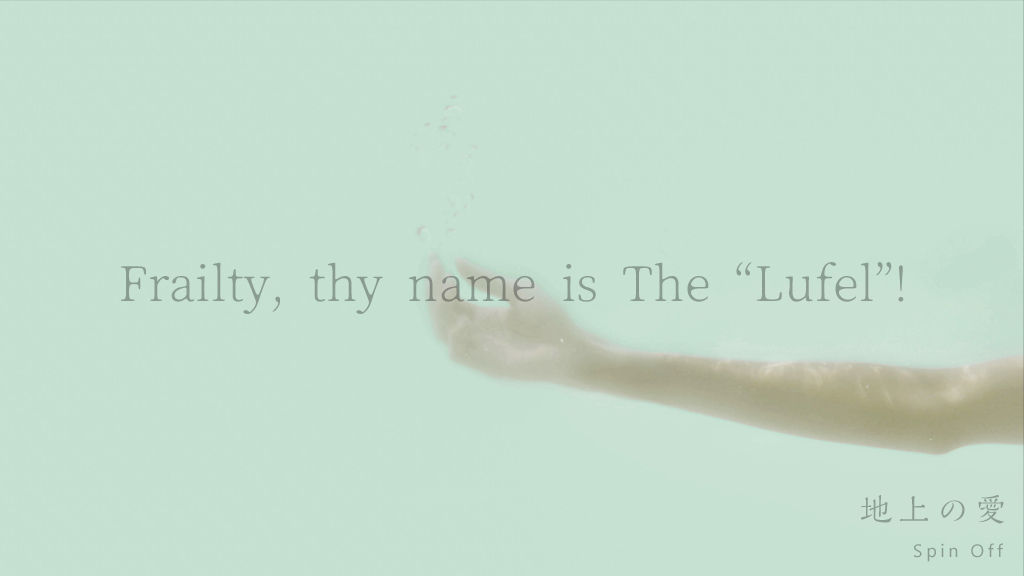Frailty, thy name is The “Lufel”!
scene.4 魔王の憂さ晴らし
「いかがいたしましょう」
「……場所が悪い」
「撤退も視野に入れて……」
「已むを得まい、ここでの戦闘は避けたい」
「かしこまりました、では待機いたします」
地上においてエデンの天使がアビスの悪魔と衝突することは少なくない。下級三隊八級の大天使はここ、地上が持ち場なのだ。同じく、地上に暮らす人間の魂を狙う悪魔にとって、ここは狩場であり必然的に顔を合わせる機会は多い。しかし大天使は、人間の今際の際に祈りを捧げ、魂をエデンへと導くために遣わされているに過ぎないため、基本的に戦闘力は低い。
そこで、小競り合いなどが始まった場合、エデンの戦闘部隊が駆け付ける。通常であればそこで悪魔が退き終わるはずだが、今回は相手が悪かった。
「おやおや……大天使長さまのお出ましかと思えば、撤退とは片腹痛いな」
「おまえと違ってこちらは制約が多くてな」
「気にせず剣を召喚すれば、こんな所で立ち話をする手間が省けるんだが」
「躾のなっていない闇子がいなければ、そもそも戦う手間すらいらん」
「おれはこの場を焼き払っても構わんがねえ……」
「生憎わたしは行儀が良くてな」
最初は下級天使と小悪魔の小競り合い、だった。当然お互い援護を頼む。駆け付けた天使の戦闘部隊もはじめは分隊だったが、小悪魔の危機に現れたのはアビスで暇を持て余していた上級悪魔だった。これは拙いと思った天使の分隊が分隊を呼び一個小隊ができあがる。しかしここは荒野でも砂漠でもなく、人間で賑わう市場のど真ん中だ。下手に手を出せば上級悪魔がどう出るかわからない状況の中、ルフェルに緊急通報が入った。
「一個小隊を抱えながら、手も足も出ないとはとんだ見掛け倒しだな」
「ここが廃村や廃鉱ではないことに感謝してもらいたいものだが」
「戦えない場所がある戦闘部隊に何の価値があるのかねえ」
「わざわざ戦えない場所を選んで現れたとしか思えんがな」
「……相変わらず口の減らねえ野郎だな、ルフェル」
「相変わらず血の気が多いようだな、ベリアル」
一瞬、天使の一個小隊がざわついた。姿を見るのは初めてでもその名を知らない天使はいない。 “光をもたらす者” と呼ばれる “暁の天使ルフェル” と火花を散らす相手が、かつて “すべてを欺く者” と呼ばれ、ルフェルに次ぐ力と権力を有した “敵意の天使ベリアル” だったと知って天使たちは驚いた。上級悪魔どころではない。
ルフェルと変わらぬ長身に漆黒の髪。ルビーのように紅く煌めく瞳は禍々しさを孕み、全身からあふれ出る邪気が辺りの空気を黒く滲ませる。しかしその肌は白く、端整な顔立ちがよりいっそうベリアルの残忍さを際立たせた。
「まあ、おれは暇が潰せるなら何でもいいんだけどな」
「わたしは潰す暇すら惜しいのだが……」
「……相変わらずスカした野郎だな」
「お褒めに与り光栄だ」
五十名からなる天使の一個小隊は、ルフェルの余裕さえ窺える様子に安心していたが、戦闘部隊の最高司令官であり大元帥のアヴリルだけはこの状況をむしろ心配していた。確かに大天使長は絶大な力を誇る方ではあるが、今回ばかりは分が悪い……いくらベリアルが元熾天使とはいえ、いまは……アビスの帝王だ。邪悪さ加減で言えばどちらも引けを取らないが、大天使長は……
「間怠いな……いくらあんたが強くても、ここじゃおれに勝てねえよ」
「その割には一向に斬り込んで来る気配すらないようだが」
「……その手に乗ると思うなよ」
そう言うと、ベリアルは市場を行き交う人間に目をやり、ルフェルの視線を一瞬迷わせた。
── やられた。
アヴリルは、思った通りの展開に溜息を吐くしかなかった。剣術の腕で言えば圧倒的に大天使長が優位だ。この距離ではベリアルも魔法の詠唱はできない。しかしこの人混みだ。剣を召喚するだけの広さがない。周りにいるのが天使と悪魔だけなら、ためらうことなく剣を払っただろうが、人間に当てるわけにはいかない。かといって普通の剣ではダメージが一切通らない……大天使長の慎重さが仇になったな……
殺気立つ天使の戦闘部隊が一斉に立ち上がった。
「あんたんとこの兵隊は、事態の飲み込めない痴れ者揃いかよ」
ベリアルはそう言いながら、腕の中に納めた小さなこどもをゆっくりとなでた。
「……放せ」
「剣の召喚はできねえ、魔法も使えねえ、普通の剣じゃ効かねえ、そのうえ人質まで取られた気分はどうだ?」
「もう一度だけ言おう、放せ」
「勘違いすんなよ……あんた、いまそんなこと言える立場だとでも思ってんのか」
ベリアルの手が、その腕の中の小さな首に掛かる。
「最終手段の殴り合いも、この間合いだと首をひねるほうが速いだろうな、大天使長さまよ」
「……要求を飲もうか」
「ふっ……話のわかる大天使長さまだな。後ろの天使全員殺せっつったら殺すのかよ」
その程度の要求であればふたつ返事で飲むだろう、と後ろに控えるアヴリルと戦闘部隊の全員が思った。
「殴らせろ」
その要求はさすがに無茶が過ぎるのでは……と後ろに控えるアヴリルと戦闘部隊の全員が思った。
「……いいだろう」
後ろに控えるアヴリルと戦闘部隊の全員が耳を疑った。
「まずはこどもを放してもらおうか」
「放した途端、殴り掛かられるのもなあ……」
「随分と信用がないんだな」
「あんた、その辺の信用を周りから得られてるとでも思ってんのか……」
神々に忠誠を誓い、忠義を尽くす上級三隊の中でも、熾天使という一級の身分を誇れる者は決して多くはない。その中において特級のルフェルの次に名を馳せたベリアルは、いわば神々の次に力を持っていたと言っても過言ではなかった。ルフェルさえいなければ、間違いなくベリアルが大天使長の座に就いただろう。それだけ他の熾天使に比べ圧倒的な力を持っていたベリアルには、不幸にもルフェルという難攻不落な壁が立ちはだかった。
地上の人間には優しいが、同族には一切の容赦もなく、まだ神々のほうが慈悲深いのではと思えるほどに無慈悲な大天使長ルフェル。職務に忠実でただひたすら真面目なだけの、融通の利かない絶対的権力者の存在が煙たくないはずがない。ベリアルが堕天した一番の理由は、エデンの厳粛な掟に縛られながら、忠義を尽くすことが面白くなかったからだが、ルフェルの存在が気に入らなかったというのも大きな理由のひとつだ。
事実、ベリアルは堕天したあとあっという間にアビスをひれ伏し、絶対王として君臨することとなった。それだけの力を持つベリアルが、唯一敵わなかったルフェルを殴りたいと思う気持ちはわかる、と後ろに控えるアヴリルと戦闘部隊の全員……とまでは言わないが、少なくともアヴリルにはベリアルに同情する気持ちはあった。まだ、この時は。
ベリアルは小さなこどもの手の甲に、ひとつ魔法を掛けてから放した。こどもは人間で賑わう市場へと吸い込まれ姿が見えなくなった。
「……何をした」
「おれと魂をリンクさせたんだよ。つまり、おれが殴られればあのこどもも痛いし、おれが死ねばこどもも死ぬ」
「なんとも用意周到なことだな」
「これくらいしておかねえと、あんただけは信用できねえからな」
「力でねじ伏せる自信がない、と言っているように聞こえるが」
「その言葉、後悔させてやるからな」
さすがに人間であふれ返る市場のど真ん中では都合が悪い、と少し離れた所まで移動したルフェルとベリアルを追い掛ける戦闘部隊は、なぜか俄かに盛り上がっていた。ベリアルの名前しか知らない若い天使たちは、エデン史上最凶と言わしめた大天使長が殴られる様に興味津々だったのだ。
常に冷静沈着で驚くこともなく、どんなことがあっても表情ひとつ変えることのない、残酷なまでに正しく忠実で無慈悲な絶対的権力者が、人間のこどものために殴られるなど想像すら付かない。と同時に、大天使長の絶大な力でもってすれば、少々殴られたくらいではびくともしないだろう、とも思っていた。
ベリアルの全盛期を知るアヴリルはまったく楽観視できず、念のためにと救護班を呼び付けた。
「さて……アヴリル。おまえの手駒、止めに入ったやつから殺すからな」
アヴリルは振り返り、戦闘部隊に「手を出すなよ」と言い含めた。
「あんた、こういうときでもそのツラ崩さねえんだな」
「こういう顔なんだろうよ」
「言っとくけど、水晶は守ってくれねえからな?」
「……どういう意味だ?」
次の瞬間、ベリアルの硬く握られた拳が弧を描くように右側面から頬に入り、ルフェルは勢いよく吹き飛んだ。
「こういう意味だよ」
地面に落ちて転がったルフェルはその衝撃に驚いた。いや、確かに不意を突かれたのは事実だが、だからといって完全に油断していたわけでもない。もう少し力を受け流せるはずだが……からだを起こすと、口からパタパタッと血液がこぼれる。どういうことだ……魂が中にあるとでもいうのか。
「ねえ……ちょっと、なんで大天使長さまから……血が流れてるの……」
戦闘部隊の天使たちはみな茫然とその姿を見ていた。天使の魂はからだから切り離され……エデンの水晶に守られているはずでは……
「大元帥さま!」
「……まさか、水晶の魂を召喚しているのか」
「召喚!?」
「本人のからだを依り代にして魂を……」
「では……いまの大天使長さまは」
「ほぼ生身と変わらないだろうな……」
「血の味なんて、知らなかっただろ?」
「……そうだな」
「まさかこんなに簡単に転がるとは思ってもみなかったぜ」
「実は、見た目より軽いんだ」
「立てよ……まだ始まったばっかりじゃねえか」
立ち上がったルフェルは脚に力を入れ今度はしっかりと構えた。二発目をあごにもらい、衝撃で足場が若干ずれたものの吹き飛ぶほどではない。ベリアルの腕の速さは見切れるが……避けてはいかんのだろうな、と思ったところで三発目が左頬に入り、派手に口の中を切った。口内に広がる薄ら甘い鉄の味。飲み込まないよう吐き出すと、地面に赤い染みができる。
これは……面倒なことになりそうだな。水晶の魂が魔法で転生でもされてるのか……多少血が流れたところで困りはせんが、このいざこざに駆り出されて今日の職務が片付いてない。結晶関係の書類の確認は部屋に持ち帰れば済む話だが、このあとの審理の立ち会いは外せん。とりあえず四発もらったことは憶えておこう。ああ、こどもに掛けたという魔法はいつまで効力があるんだろうか。五発目……本当に容赦ないな。……六発目。
到着した救護班もまた、戦闘部隊の天使同様ただ茫然とそれを見ていた。
「大天使長さま……血まみれじゃない……」
フィールは慌てて薬箱を開き、触媒となる薬草や木の実を取り出した。しかしこれで使える回復魔法は、魂を持たない天使のからだの傷を塞ぐことはできても……生身の治癒はできない。
一切抵抗せず、ただされるがままのルフェルの姿は、信じられないほど大きく損傷し、疲労しているように見えた。戦闘部隊も救護班も、天使のからだからおびただしい量の血液が流れるのを初めて目の当たりにし、恐怖に言葉を失った。あの大天使長さまが……常に冷静沈着で、何があっても表情ひとつ変えることのない大天使長さまが……残酷なまでに正しく無慈悲なはずの大天使長さまが……人間のこどものために血を流している……
「……ほんとに可愛げのねえやつだな。少しくらい鳴き声あげられねえのか」
「そういうのが……お望みなのか?」
「そうだな、とりあえず特級の熾天使の喘ぎ声でも聴かせてもらおうか」
「おまえがその手で喘がせればよかろう」
「そのカラダ、一番感じる部分はどこなんだ?」
「教えて欲しいなら頼めばどうだ」
「……そそるねえ」
ゴキッ……とルフェルのみぞおちで鈍い音が鳴った。
「……う…ぁ」
「イイ声で鳴くんだなあ……さすがにイッたみたいじゃねえか」
みぞおちに喰い込んだ拳は胸骨を砕き、ルフェルは口から鮮血を散らせそのまま崩れ落ちた。
……まいった…痛みに耐えられんわけではないが……物理的に壊されるとからだの制御が難しい。いまの音と、この感触から胸骨辺りが折れたようだが、まさか脚の力が抜けるとは……少々血を失っても困らんと思ってはいたものの、さて、どこまでが少々の範囲なのか見当も付かん。何より早く終わらせんと、このあとの職務に支障を来す。
周りで見ていることしかできない戦闘部隊も、救護班も、もう限界だった。恭謙からは程遠く、謙遜することを知らず、謙虚さの欠片もない大天使長がいま、目の前で地に膝を着き、その両手を着いて肩で息をしている。深く切ったまぶたからは止め処なく血が流れ、折れた肋骨は皮膚を食い破り、肌を突き抜け新たな傷を作る。
「大元帥さま!」
「……手を、出すなよ」
「大元帥さま!!」
「……大天使長が守ったこどもを犠牲にするわけにはいかない!」
「しかし……これでは大天使長さまが」
「手を!……出すな!」
アヴリルなら……熾天使であり戦闘部隊の長であるアヴリルなら止められる。実質いまのエデンではルフェルの次に腕が立つのだ。周りの視線が一斉にアヴリルに注がれる。この広い場所でなら剣も召喚できるが、しかし……いま手を出すことを一番望まれないのは大天使長本人だ……
「あんたんとこの兵隊は本当によく躾けられてんだなあ……自分たちの大将が死に掛けてるってのに、たかが人間の子ひとりのために誰も手出しして来ねえ……泣けるねえ」
「お褒めに与り……光栄だ」
「まあ、おれもそろそろ飽きて来たから終いにさせてもらうぜ」
そう言うと、ベリアルはひとつ魔法の詠唱をした。
「本来はカラダ使うよりこっちのほうが得意でねえ」
「ほう……嗜虐がお好きなのかと思ったが」
「膝着いて言うセリフじゃねえな」
「喘ぎ声じゃなくて…悪いな」
ベリアルが膝を着くルフェルの顔を蹴り上げると、そのままルフェルのからだは勢いよく跳ね地面に転がった。ぐったりと動かないルフェルの右手を踏み付け、すり潰すよう躙りながら、ベリアルは心底嬉しそうにくくっ、と笑う。
「お楽しみの最後にひとつ教えてやろう」
「……楽しんでいただけて…何よりだ」
「こどもに掛けた魔法は……おれが抱えていた間の記憶を消す魔法だ」
「……なるほど…よほどわたしが……恐ろしかったと見える」
「ほざけ、たまらなくて鳴き声あげたくせしやがって」
「……相変わらず……やることが汚いな」
「ふっ……いまさらだろう? まあ仕返しも怖いから、その右手砕かせてもらうぜ」
剣を召喚するならいましかない。
こどもが無事なら何も遠慮することなどないのだ。奢られっぱなしで逃がしては、礼をする機会を失する。召喚さえできればその勢いで薙ぎ払うだけだ。時間は要らん。時間は要らんが……
なんとか右手を動かそうとはするものの、もうルフェルには踏み付ける足を跳ね除ける体力が残されていなかった。靴の下にある右手が突然激しく圧迫され、みしっ……と骨を軋ませる。ベリアルはルビーのような紅い瞳をいっそう煌めかせ、口の端を吊り上げて嗤いながら「またな」と言って地面をトンと蹴った。
ベリアルの姿はその場で黒く霧散し、ルフェルの右肘から指先までが激しい破砕音を立てて一気に砕けた。慌てて走り寄るアヴリルと戦闘部隊。フィールは薬箱を抱え、救護班はそれぞれ治療器具を手に掴み、血にまみれ動かないルフェルを一斉に取り囲んだ。
ああ……審理の立ち会いに……間に合うんだろうか……しかし弱ったな…これではペンが…握れん……
───
目を覚ましたルフェルは飛び起きようとして、その激痛に阻まれた。
「大天使長さま……!」
フィールは瞳いっぱいに涙を浮かべながら、ルフェルが目を覚ましたことに安堵し、アヴリルもまたほっとして胸をなでおろした。エデンの診療所で目覚めたルフェルは、医療部から状態の説明を受ける。胸骨を砕かれ、肋骨を三本折られ、橈骨と尺骨と手根骨と指骨五本を砕かれた挙句、最後に蹴り上げられた際に頬骨まで陥没させられたルフェルの機嫌がいいはずがなかった。
聞くところによると、あの日から五日間も経っている。その五日分の職務は果たされることもなく、しっかりと積み上がっているだろう。寝ている場合ではないが、如何せんからだがまったく動かない。声を出そうとするとみぞおちが痛み、あの時ベリアルに言われたことを思い出してはさらに機嫌が悪くなる。
魂をその身に召喚されたままエデンに連れ帰るわけにも行かず、かといって地上では応急処置しか施せず、その場にいた六十二名は息をすることも忘れ、必死に大天使長の無事を祈った。水晶に戻った魂を確認したモーリアが、その魂の衰弱ぶりと覇気のなさに驚き、アヴリルたちに厳しい声で「覚悟なさい」と告げたほどに、その時ルフェルは危篤に陥っていた。
さらに具合の悪いことに、ルフェル本人が昏睡状態にある間は魂の修復ができないという。どれだけ水晶を浄化しても、その魂の呼び掛けに昏睡したからだが呼応せず、いわば主を失った状態の魂は主を求め衰弱して行くというのだ。毎日、毎日、五日間祈り続けた。その戦闘部隊と救護班、総勢六十名が、目を覚ましたルフェルの姿をひと目見たいと思うのは当然だった。
……随分と部屋の外が騒がしいが、一体何事なんだ……こんな所で油を売る暇のある者がいるのか……羨ましい…経費を削って欲しい部署はどこだ……直属の連中なら全員まとめて薙ぎ払ってやろう…ともかく勤めに戻れ……
その様子に気付いたアヴリルがルフェルをなだめた。
「まあまあ、大天使長……苛立つお気持ちはわかりますが、彼らも必死だったので大目に見てやってください」
人間のこどものために一切抵抗することなく、なぶられ、いたぶられ、血まみれになりされるがままだった大天使長を、見ていることしかできず、助けることもできず無力感に襲われながら、きつく噛み締めたくちびるを震わせ、握り締めた手に爪を食い込ませ、泣きながら必死に耐えた天使たち。
永遠の命を持っているとはいえ、魂を召喚されたまま地上で留めを刺されたら、大天使長がいなくなってしまう、とその恐怖に言葉を失い絶望感に打ちのめされていた天使たち……この五日間、眠ることもなく祈り続けた戦闘部隊と救護班。
「面会を、許してやってはいただけませんか?」
そして入口のドアが開かれ、まず救護班がルフェルの無事を確かめひとりずつ労いの言葉を掛けて行く。それから戦闘部隊が現れルフェルの顔を見ながら涙し、口々に「申し訳ありませんでした」と謝っては去って行く。
……労いはわからんでもないが、なぜ戦闘部隊はみな謝罪をして行くんだ?
“エデン史上最凶と言わしめた大天使長が殴られる様に興味津々” だった戦闘部隊の天使たちはもう、二度と大天使長が殴られる様を見たいとは思わないだろう。
普段より強力に浄化され続けた水晶と生命の樹の実によって、それから二週間でルフェルは全快した。砕かれた骨も元に戻り、同族には一切の容赦もなく、常に冷静沈着で驚くこともなく、どんなことがあっても表情ひとつ変えることのない、残酷なまでに正しく忠実で、まだ神々のほうが慈悲深いのではと思えるほどに無慈悲な、恭謙からは程遠く、謙遜することを知らず、謙虚さの欠片もない、ただひたすら真面目なだけで融通の利かない絶対的権力者は完全復活を遂げた。
「……さて」
殴られた回数二十九回、蹴られた回数十二回、砕かれた骨多数。
ルフェルは静かにメモを書き残した。