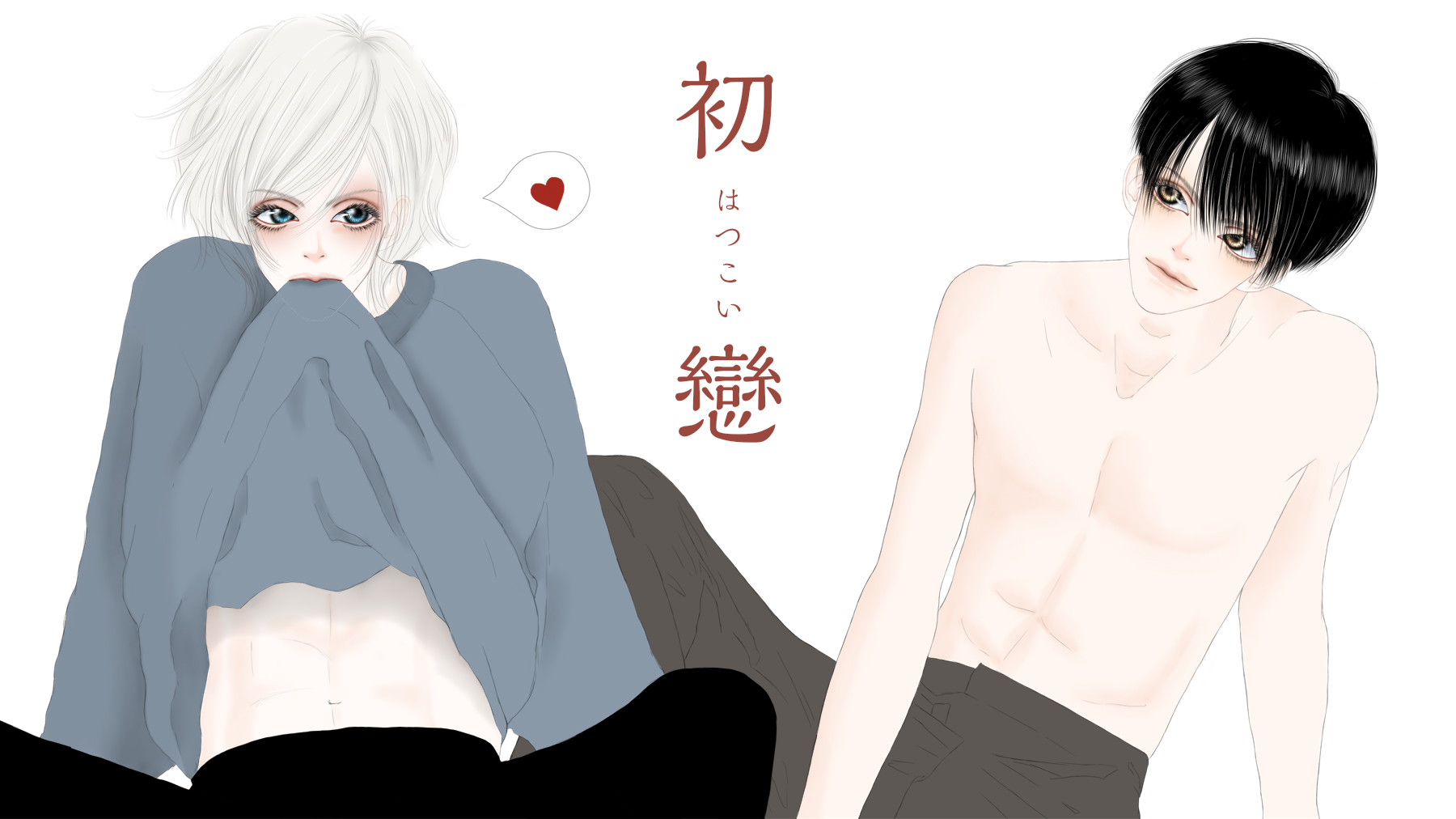第六十六話 人と屏風は直ぐには勃たず
「…どんな顔してればいいんだろう」
「普通でいいよ」
「普通って言われても……」
普通でいい、と言いながら硬い表情を見せる久御山のあとを着いて行く。ふと目の前が明るくなり、開かれた扉の向こうを恐るおそる覗き込んだ。
「……ケンソー」
「おう、来たほうが早いって言われたから来たけど」
「骨折れてんのに堪忍な」
久御山とシロくんの声を聞きながら、両足が床に貼り付いたみたいに動かなくなった僕は、部屋と廊下の境界線で立ち止まったまま目を泳がせた。肩を軽く払われ振り返ると、僕のせいで部屋に入れない桐嶋先生と紅さんが頼りない笑顔で僕を見ていた。
「あ、すみません…」
「入らないのか?」
「…はい、あの……いいんですか?」
「せっかく来てくらはったんやろ? 入って入って」
桐嶋先生と紅さんに促され、僕はなるべく気配を消しながら部屋に入った。僕に気付いたシロくんが穏やかに笑い掛ける。
「湊、元気やった? 指、どうや?」
「うん、大丈夫」
「それを桐嶋の前で訊くかねえ」
「……その節は、本当に申し訳ない」
桐嶋先生は床に目線を動かして、とにかく久御山と目が合わないようにしているようだった。申し訳ないと思うなら、久御山にじゃなくて僕にじゃないのかな…
病室のベッドの上には ──
何も言わず、薄く開いた目でただぼんやりと天井を見つめているクロくんがいた。
「黒檀、リンゴジュースとオレンジジュース、どっちがええ?」
ベッドのわきでエコバッグの中を探りながら、紅さんがクロくんに訊く。
「クロ、リンゴジュースのほう好きやから、うちにオレンジジュースちょうだい」
シロくんが紅さんに手を伸ばすと、紅さんは瓶に入ったオレンジジュースをシロくんに渡した。それから同じ瓶に入ったリンゴジュースをクロくんの顔の前でそっと揺らし、ふふっと笑いながら紅さんはその手を引っ込めた。
「いまは欲しない気分やねんな?」
クロくんは天井を見つめていた。
───
病棟にある小さなロビーのソファに腰をおろした僕たちの口は重かった。
「…なんか飲む?」
自販機の前で紅さんが久御山に手招きをする。紅さんと久御山は、ほんの少し自販機の前で何か話をしているような素振りを見せて、それからカップのコーヒーを手に戻って来た。
「ほら、湊」
「ん、ありがと」
「……で? こんなところでそんな辛気くさい顔してたら余計心配でしょ」
「そうだな……結論から言うと」
「え、それは怖いから順番に言ってよ…」
「なんだそりゃ……転落事故から二週間で、黒檀は意識を取り戻した。大きな山は越えたと思ったんだが……どうも、脳が腫れて圧迫されてるからなのか、記憶がないんだ」
「記憶がない? 何歳頃の?」
「……全部…名前はおろか、言葉すら憶えてない状態で」
「え、何よ、自分が何者なのかさえわからんってこと? 産まれたばっかり?」
「そうだな、泣いて存在を主張する赤子のほうがマシなくらいだ」
「……声、出ないの?」
「検査してみないとわからんが…いまのところは出てない」
「意思疎通も図れないってこと?」
「そうだな…」
久御山と桐嶋先生の話が聞こえてるのかどうなのか、シロくんは遠くを見るような目でソファに身体を沈めたまま動こうとしなかった。受け止めろって言われても難しいよな……産まれた時からずっと一緒だったひとが、自分のことすら憶えてないなんて…
「……湊、どうした?」
「久御山が僕のことだけ憶えてなくて……そのうえ言葉まで忘れてたらって…思ったら…」
苦しくてパタパタと涙がこぼれた。絶対に忘れられない、別れを覚悟したあの日が甦る。久御山はおもむろに立ち上がると、僕の膝の上に腰をおろし、僕の頬を舌先で拭った。
「…っ!」
「ちゃんと思い出したよ。大丈夫、クロも思い出すよ」
───
肋骨を折ってる久御山を家に残し、僕はクロくんに逢うためひとりで病院に来た。大丈夫だって何度も言ってたけど、大丈夫なわけがないんだよ。そうじゃなくても久御山は平気で無茶をするヤツなんだから、こんなときくらい安静にしてて欲しい。帰ったら気の済むまで久御山を構うことを約束し、晴れて僕は単独での外出許可を得た。
受付で面会の手続きを済ませ病室のある病棟のエレベーターに乗ると、なぜか心細くなった。ダメだダメだ、こんな弱気でどうする。普通に振舞うって決めたじゃないか。ネガティブな気持ちは伝染する。笑って笑って。
病室の扉を開けると、珍しく誰もいなかった。あれ? シロくんもいないのか。
「クロくん、気分どう?」
いま反応がなくても、何がきっかけになるかわからない。普通に話し掛けているうちに、気付くことがあるかもしれない。そう思いながら僕はいままでどおり、クロくんに話し掛けた。
「今日もすっごく暑いよ…ここに来るまでで汗ダク」
シャツの襟をつまんでパタパタ扇いでみたところで涼しくなることはないのに、ついそうしてしまうのはクセみたいなものなのかな。病院の中は適温のはずだけど、外から来たばかりだと身体が慣れるまで時間が掛かる。
その時クロくんの目がゆっくりと動き、驚いて言葉を失っている僕と目が合った。
「……クロくん!?」
ぽっかりと穴が開いていただけのクロくんの瞳が、意思を持って何かを探しているような、求めているような、そんな生命力を感じさせながら僕の顔をじっと見ていた。
「クロくん、わかる? 僕のこと」
僕から目を逸らさないクロくんは、何かを訴えているような気がした。でも、言葉を発しないクロくんの要望を、僕には汲み取ることができない。クロくんの枕元にあるスイッチを押して、僕は看護師さんを待った。
病室の扉を開けた看護師さんと一緒に、シロくんと桐嶋先生と紅さんも飛び込んで来た。
───
「本当だよ、見間違いなんかじゃないよ…」
「嘘だなんて思ってないよ」
「だって……」
病院から久御山の家へ戻り、僕は嘘のような本当の話を切々と訴えた。
病室に看護師さんとシロくんたちが駆け付けたあと、クロくんはまたぼっかりと穴の開いたような目で天井を眺め始めた。みんなで一所懸命声を掛けてもそれは変わることなく、まるで誰ひとり病室にいないみたいに、クロくんはぼんやりと病室の空気に同化した。
「湊ひとりだったら反応するのかな」
「考え難いけどね……僕が一番関係が薄いっていうか」
「むしろ、つながりが濃い人間を拒絶してるんじゃないか?」
「なんで? そんなことする意味なくない?」
「んー…あの時クロがさ」
久御山はクロくんが転落する前に言っていたことを思い出しながら話した。クロくんがシロくんを嫌いだったなんて、そんなことあるわけがない。だって、あんなに通じ合ってたのに……
「……シロが余計なこと気にしないように、なんじゃないかな」
「シロくんのためにいなくなった、って思われないように?」
「うん、奪い合うことに疲れたってのも事実なんだろうけど」
「奪い合うって……譲り合ってただけだよ」
「だからさ、一方的に譲られたらシロだって苦しいじゃん」
それで……もうすべて終わりにした以上、自分を甘やかす存在を拒絶してるってこと? 無意識に? これからずっと、シロくんたちを視界の外に追いやって生きて行くの?
「……僕、しばらくクロくんに付き添ってもいいかな」
「うん、シロたちに話してみたら?」
「そうする…何か変わるといいんだけど」
「その前にオレの気の済むまで」
「ああ、そういえば約束してたね」
「湊を凌辱して涙目にさせながらアンアン鳴かせてエロい顔でイかせたい」
「そこまでの契約は交わしてない」
───
「おはよ、クロくん」
面会が始まる八時に病院へ行き、クロくんの様子を確かめる。シロくんも、桐嶋先生も、紅さんも僕の希望を快く受け入れてくれたけど、心の中は穏やかじゃない気がする。だって限りなく他人に近い僕がそばにいるなんて、いまのクロくんの容態を考えると不安でしかないだろう。
「のど渇いてない? 水かリンゴジュース飲む?」
病院側の話だと、もう自力で飲み込むことができるってことだったけど……右手にペットボトルの水とパックのリンゴジュースを持って、クロくんの顔の前で軽く振ってみる。ゆっくり瞳を動かし僕と目が合ったクロくんは、それから僕の手に握られた水とリンゴジュースをしげしげと眺めた。
片手でふたつ持ってるとわかりづらいな、と片方ずつ振ってみることにした。なんとなくリンゴジュースを見てる目のほうが大きく開いた気がして、パックにストローを挿して口元に運んだ。吸引する力って、あるのかな……
こぼれてもいいように顔の下にハンドタオルを敷いてしばらく待ってると、クロくんの口唇がヒクっと動き、ストローに反応してるのがわかった。本当は、こういうのシロくんが見届けたかっただろうな……なんとなく申し訳ない気持ちに圧し潰されそうになっていると、クロくんが小さく咳込んだ。
「…っ、大丈夫!?」
骨折した身体で咳込むとか、大惨事なんじゃないか!? ジュース、気管に入っちゃった!? 焦る僕の鼓動を余所に、クロくんはもう一度リンゴジュースを吸い込んで、僕の顔を見た。あ、なんか嬉しそうな顔してる気がする……
でもやっぱり、僕以外のひとの前では天井を眺めてるだけだった。
久御山が言うように、僕が遠い人間だから拒絶しないんだとしたら、医者や看護師さんのほうがもっと遠いと思うんだけど、病院の中のひとたちにもクロくんは無反応だった。
いまクロくんは、何を思ってるんだろう。
***
「クロ、どうだ?」
ひとりで行くという湊を説き伏せ、今日はオレも一緒にクロの様子を見に来た。ずっと引っ掛かってることを確かめたかったんだが、無機質な部屋で横たわるクロの姿を見ると、放っておいたほうが親切なのかもな、という気もして来る。
最初は頚髄損傷による運動機能の麻痺は避けられないだろう、という話だったが、幸い骨折した頸椎の場所や状態に救われたらしく、以前と同じ生活に戻れるだろう、と診断されたそうだ。まあ、別にアスリートだったわけでもないから、多少手脚が動かし難くても生きてりゃ問題ない。
ただクロにとっては……生き延びてしまったことが何より残酷なのかもしれない。
「……やっぱり湊以外の人間がいると無反応なんだな」
「そうだね……何がスイッチになってるんだろう…」
仰向けのまま微動だにせず、ただそこにいるだけのクロは……本当に言葉すら忘れてしまったのか?
「湊、ちょっと」
「何?」
「クロのほう向いて立ってみてくれる?」
「……? いいけど、何するの?」
ベッドのそばに湊を立たせ、その肩越しにクロとの距離を確かめる。まあ、これくらいの距離なら大丈夫だろ。
背中から腕を回し、湊のシャツのボタンを順番に外した。夏だからこれ一枚……シャツの下はもう素肌だ。
「ちょ、久御山……何してんの!?」
「しーっ…とりあえず目つむってて」
「いやいや、とりあえずって言われても!」
肩からシャツを滑らせ腕からそっと抜き取る。細いくせにイイカラダしてんだよなあ……身長と骨格の賜物なんだろうが、肩幅もあるし手脚長いし……っと、ここでオレが欲情してどうする。
ベルトを緩めチノパンのファスナーをさげると、さすがに湊がオレの手を掴んで止める。
「久御山!?」
「だいじょーぶだって、挿れたりしないから」
「当たり前だろ! っていうか何がしたいんだよ!」
「ストリップ」
「は?」
「ス・ト・リ・ッ・プ」
「自分が脱げばいいだろ!? なんで僕を」
「だっていまは湊にしか反応しないんでしょ?」
そう言うと、湊はおとなしくなった。さすが、賢いヤツは察するのも早いな。
ゆっくりチノパンを足首までおろしボクサーパンツのゴムに手を掛けると、やっぱり湊はオレの手を掴んで止めた。
「ちょっと待って、まさかパンツまで脱がせるの!?」
「そりゃそうだろ」
「誰か入って来たらどうするんだよ!」
「鍵掛けてあるから安心して」
「いや、すでにこの状態が安心できない」
「オレしかいないようなもんだよ?」
「いま世界中でここが一番危険地帯だろ!」
まあまあ、と言いながら湊のボクサーパンツをギリギリまでさげると、何やら湊が反応しかけ慌て出した。いま元気になると上からはみ出すんじゃないか? オレは構わないけど……
「久御山、無理」
「まあ、そのようだねえ」
「大体、なんでおまえが脱がすんだよ……」
「えー? そのほうがクロも喜ぶかなあと思って」
しょうがない、恥ずかしがり屋の湊がここまで協力してくれたんだからこれ以上掘り下げるのはやめておこう。スコポフィリアのクロが興味を持ってくれるかもな、って淡い期待があったんだが……性質に根付いた部分すら忘れてるのか。
「……やることがえげつないわ」
「…っ!?」
ベッドを覗き込むと、苦々しい顔でクロがオレを睨み付けていた。
「……最後まで見たい?」
ニヤッと口角を上げると、クロの眉間のシワが深くなった。